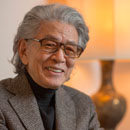五木寛之 流されゆく日々
-

連載10439回 ドン・ファンとは何者か <3>
(昨日のつづき) テレビで、「ドンファンって何?」という街頭インターヴューをやっていた。 「金持ちジイさんのことでしょ」 と、女子高生たちが笑う。若い人たちの間では、なんとなくそういうイメー…
-

連載10438回 ドン・ファンとは何者か <2>
(昨日のつづき) 紀州のドンファンという文句が巷にあふれ過ぎて、紀州のイメージが変なふうに世間に受けとられるのは困ったことだ。 私たちの若い頃は、紀州の作家といえばすぐに佐藤春夫の名前が浮かん…
-

連載10437回 ドン・ファンとは何者か <1>
スターバックスで休んでいると、隣りのテーブルで女子高生らしき娘たちが大声で喋り合っている。 とても文庫本を読みつつコーヒーを楽しむ雰囲気ではない。 「どっかにドンファンじいさん、いないかなあ。…
-

連載10436回 記憶の曖昧さについて <5>
(昨日のつづき) 父親は小学校の教師だったが、学生時代からの剣道の有段者だった。 小倉師範学校の頃は、それなりに剣道の選手として鳴らしていた、というのは本人の話だから当てにならない。 以前…
-

連載10435回 記憶の曖昧さについて <4>
(昨日のつづき) こうして幼児期から小学校入学までの頃のことを思い返しても、やはり曖昧なところが多く残る。 たとえば、それが何年で何月頃のことであったか、というような点である。 両親が健在…
-

連載10434回 記憶の曖昧さについて <3>
(昨日のつづき) 小学校に入学するあたりから、記憶はかなりはっきりしてくる。 ソウル(当時の京城)に移ってからは、南山という高台の中腹の官舎に住んだ。 父親が南大門小学校という学校に移った…
-

連載10433回 記憶の曖昧さについて <2>
(昨日のつづき) 小学校にあがる前のことだから、5歳か6歳の頃のことだろうか。 両親とともに韓国の寒村に住んでいたことをおぼえている。たしか日本人は、駐在所の巡査夫婦ぐらいで、あとはすべて土地…
-

連載10432回 記憶の曖昧さについて <1>
人の記憶は、いったいどの位まで幼児期にさかのぼれるのだろうか。 私の知人の一人に、1歳の時の記憶があざやかに残っている、という人がいる。 1歳の誕生日のお祝いに、親戚の人が子供用の三輪車をプ…
-

連載10431回 今いちばん怖いもの <5>
(昨日のつづき) きょうの日刊ゲンダイ(6月15日付)13面には、『認知症は予防・改善できる』という記事がのっている。 6月14日は<認知症予防の日>だそうだ。 そんな日があるとは知らなか…
-

連載10430回 今いちばん怖いもの <4>
(昨日のつづき) いわゆるボケや、アルツハイマー病が怖いのは、認知機能が劣える、ということだけではない。 固有名詞や年号は忘れても、自分の思想や思い出は語ることができる。その時代の空気感や、世…
-

連載10429回 今いちばん怖いもの <3>
(昨日のつづき) 月曜日の「日刊ゲンダイ」の13面に、バカでかい見出しがでていた。 <バイオフィルム産生抑制が アルツハイマー病予防につながるか> という医療記事である。これだけ大きなスペー…
-

連載10428回 今いちばん怖いもの <2>
(昨日のつづき) 先週の各新聞に、高齢者ドライバーの免許問題が大きな見出しで報じられていた。 毎日新聞は1面トップで、 『認知症恐れ5・7万人・免許取り消しは3倍・高齢ドライバー』 と大…
-

連載10427回 今いちばん怖いもの <1>
世の中に怖いものは沢山ある。 子供の頃は幽霊が怖かった。昔の日本屋敷は、便所が廊下の先にあるのが普通だった。 居間や寝所からは、いったん廊下に出て、そこを伝って手洗いに行かなければならない。…
-

連載10426回 何歳まで運転は可能か <5>
(昨日のつづき) さて、はたして何歳まで車の運転は可能か。前にも述べたように、これにはいくつもの問題がある。 車を運転する地域のちがいも考えなければならない。大都市の錯綜する交通事情での運転と…
-

連載10425回 何歳まで運転は可能か <4>
(昨日のつづき) 一部の超富裕者層と、貧しい大衆。 世界はその方向へむかって進んでいる。この流れが変ることは当分ないだろう。 残念だが現実はそうなのだ。蟻のような大衆と、羽ばたく蝶の群れ。…
-

連載10424回 何歳まで運転は可能か <3>
(昨日のつづき) これは何度もくり返し書いてきた事だが、動態視力の劣えをしばしば感じることがあった。 新幹線に乗っていて、通過駅の駅名標示が以前ははっきりと見えていたのだ。それがスッと流れてし…
-

連載10423回 何歳まで運転は可能か <2>
(昨日のつづき) 格差という問題がしばしば語られる。 それは経済的格差が中心だ。要するに一部の超富裕層と多くの下流階級の存在がテーマである。 しかし、この格差という問題は、すこぶる難しい現…
-

連載10422回 何歳まで運転は可能か <1>
先日、90歳の婦人が交通事故をおこし、5名の死傷者をだした。新聞、テレビとも、かなりのスペースと時間を割いて報じていたから、ご存知の方も多いだろう。 破損した車の映像は衝撃的だった。車対車の事故…
-

連載10421回 東京五輪の夢の後に <5>
(昨日のつづき) 『君たちはどう生きるか』の後にくるものは、何だろうか。 それは「君たち」と呼びかけた少年たちからの返答である。 「おじさんたちはどう死ぬのか」というのが、その率直な問いではな…
-

連載10419回 東京五輪の夢の後に <3>
(昨日のつづき) かつて戦時中の私たち日本人は、「神州不滅」という物語を信じていた。 嘘のようだが、最後には神風が吹くだろうと思っていた。そう信じていればこそ、世界の大国相手に戦争をするなどと…