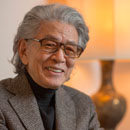五木寛之 流されゆく日々
-

連載11913回 私が本を読む場所 <4>
(昨日のつづき) 私は、どこででも本を読むことができるが、必ずしも読書に適した場所というのがあるわけではない。 前にも書いたように小学生の頃は、登下校の時間にいちばん本が読めた。少し遠回りして…
-

連載11912回 私が本を読む場所 <3>
(昨日のつづき) きょうは幻冬舎の見城徹氏と対談。 ふつう対談というのは、お互いに社交的なエールの交換から始まるものだが、そこは半世紀も前からの間柄とあって、挨拶ぬきの放談となった。 見城…
-

連載11911回 私が本を読む場所 <2>
(昨日のつづき) 机にむかって本を読む、という習慣が私にはない。 食事をしながらも読むし、寝る前には必ずベッドの中でゴロゴロしながら本を読む。 乗りものの中でも読むし、人と待ち合わせの場合…
-

連載11910回 私が本を読む場所 <1>
私は本を書くことを職業としている。 何かの書類に職業欄というのがあって、そこに記入しなければならない時には、著述業と書くことが多い。 作家、と書くのも気が引けるし、文筆家というと偉そうな感じ…
-

連載11909回 『無意識の深き底には』<4>
(昨日のつづき) 私たちは平和を愛する。戦争を憎む。 しかし、本当にそうか。 ふと、そんな妄想が頭をよぎる。 もし本当にそうなら、どうしてテレビや、小説や、話芸や、舞台などであれほど戦…
-

連載11908回 『無意識の深き底には』<3>
(昨日のつづき) 映画『ジャッカルの日』を観ながら、観客としての私は、狙撃される側よりも狙撃する側の主人公に同化している。 私たち昭和世代の子供時代、憧れのヒーローの一人は、希代の弓の名手、那…
-

連載11907回 『無意識の深き底には』<2>
(昨日のつづき) トランプ氏狙撃のニュースを耳にしたとき、私はちょうど『極大射程』(上・下)を読んでいる最中だった。 『極大射程』は私がスティーヴン・ハンターと最初に出会った作品である。それまで…
-

連載11906回 『無意識の深き底には』<1>
トランプ前大統領の狙撃事件のニュースに衝撃をうけた。あらためて、いまアメリカが置かれている状況について、考えてみなければならない。それはアメリカという国と国民の抱えているアンコンシャス・バイアスの問…
-

連載11905回 昭和の歌に情あり <5>
(昨日のつづき) 昭和は、1926年から1989年までの70余年にわたる長い時代だった。 薄命だった大正天皇の在位期間にくらべると、敗戦をはさみながらも格段に長い。 しかも、戦前、戦中、戦…
-

連載11904回 昭和の歌に情あり <4>
(昨日のつづき) 昭和前期、いわゆる戦前、戦中は、国歌、戦意昂揚歌、国民歌などの政府系の歌が幅をきかせた時代だったが、いわゆる巷の流行歌も海外進出イデオロギーの鼓吹に大きな役割りをはたした。 …
-

連載11903回 昭和の歌に情あり <3>
(昨日のつづき) 平安時代、権勢を誇った後白河法皇は、当時の有名今様歌手を自邸に招いて歌を聴き、また今様の歌い方の教えを受けた。 今様というのは、読んで字の如く当時の巷の流行り唄である。 …
-

連載11902回 昭和の歌に情あり <2>
(昨日のつづき) 前にも書いたが、作家の故・三浦哲郎さんがうたう『枯れすすき』は絶品だった。 泣くが如く、うたうが如く、嫋々と口ずさむその歌声には、文章では表現できない哀感がこもっていて、聴く…
-

連載11901回 昭和の歌に情あり <1>
昭和戦前の旧制高校生は、エリートだった。 彼らのなかには、好んで弊衣破帽を旨とする連中がいた。 今でいう汚れファッションである。腰に手拭いをさげ、下駄をはいて闊歩した。 〽デカンショ デカ…
-

連載11900回 令和の沖縄瞬間紀行 <5>
(昨日のつづき) 50年~60年代の基地反対闘争のことを、いま思いだすと、ふと暗い疑問が湧いてくる。 当時、全国に展開された基地反対闘争は、つまるところ、オラが街、オラが土地から基地を追いだそ…
-

連載11899回 令和の沖縄瞬間紀行 <4>
(昨日のつづき) 6月23日は<沖縄慰霊の日>である。 新聞・テレビなどでも大きく報じられていたが、さらに米軍兵士の性犯罪が発覚し、多くの過去の事件が非公開だったことへの批判があいついでいる。…
-

連載11898回 令和の沖縄瞬間紀行 <3>
(昨日のつづき) 以前、『マウイ島の雪』という小説を書いたことがある。 マウイは何度もおとずれた。ハワイにいく機会があっても、なぜか本島のオアフ島をパスして、マウイ島へ直行する。 半世紀以…
-

連載11897回 令和の沖縄瞬間紀行 <2>
(昨日のつづき) 前回、沖縄を訪れたとき、古謝美佐子さんが楽屋に訪ねてきてくれた。 古謝さんは私が尊敬する琉歌の歌い手で、若い頃から何度となくご一緒にステージをつとめていただいた朋友の一人であ…
-

連載11896回 令和の沖縄瞬間紀行 <1>
沖縄へいく。 講演の仕事である。 定員1700人とかいう巨大なホールでの講演ときいて、最初は辞退しようかと思った。 そもそも文士の講演なんてものは、多くて300人程度というのが常識ではあ…
-

連載11895回 私のグルメ三点セット <5>
(昨日のつづき) 私がよく口にするものの一つが餃子である。水ギョーザ、焼きギョーザ、蒸しギョーザなどの三点セットの中では、やはり月並みだが焼きギョーザだろう。 かつて満蒙開拓団の送りこまれたあ…
-

連載11894回 私のグルメ三点セット <4>
(昨日のつづき) そうだ、私たちの世代にとって欠かせない食べものの一つが漬けものである。 漬けものは、最近では食卓の脇役中の脇役といった感じになってきた。 しかし、かつて漬けものが主役であ…