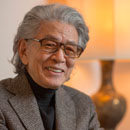五木寛之 流されゆく日々
-

連載10579回 「こころ」と「からだ」の関係 <4>
(昨日のつづき) 私は知識人ではない。本は沢山読むのだが、思想とか哲学とかいった分野の本は苦手だ。 私が知ったかぶりで喋る知識の断片は、すべて耳学問である。活字から学んだものではない。 し…
-

連載10578回 「こころ」と「からだ」の関係 <3>
(昨日のつづき) 私が生れたのは1932年である。すでに古い昔の時代になってしまった年号を使えば、昭和7年ということになる。 その1932年、満州国が建国され、五・一五事件がおこった。世界恐慌…
-

連載10577回 「こころ」と「からだ」の関係 <2>
(昨日のつづき) かなり昔のことだが『こころ・と・からだ』という本を集英社から出したことがあった。 その後、数十年にわたってあれこれと養生や健康のことを書き続けてきた。しかし、根本のところは当…
-

連載10576回 「こころ」と「からだ」の関係 <1>
このところ、あわただしい日々が続いた。年頭そうそうカンヅメ状態だったのである。 仕事が立て込むと、睡眠のリズムが大幅に狂う。もともと無茶苦茶な生活だったのが、最近、輪をかけてひどくなった。 …
-

連載10575回 現代の「3K」とは何か <4>
(昨日のつづき) 「KARADA」の「K」についても、「ポスト真実」の時代が長く続いた。しかし、いまや「ロスト真実」の渦中に踏みこんだと言っていい。 しばらく鳴りをひそめていた減塩反対論がまたあ…
-

連載10574回 現代の「3K」とは何か <3>
(昨日のつづき) 歴史は常にフェイク・ニュースにみちている。それは確かだ。明治維新ひとつふり返ってみても、本当のところは真黒だろう。フェイクでない時代など、これまでになかった。 とは言うものの…
-

連載10573回 現代の「3K」とは何か <2>
(昨日のつづき) 「カラダ」 「カネ」 「ココロ」 それぞれの3つの頭の文字が「K」になる。これが今の時代の3つの問題点ではないか、と昨日のこの欄で書いた。「健康」「経済」「心」と言いかえて…
-

連載10572回 現代の「3K」とは何か <1>
かつて時代を象徴する言葉の一つに、「3K」というのがあった。 「キツイ」 「キタナイ」 「キケン」 それぞれの頭文字のKをとったものらしい。苛酷な労働現場の状況をいうフレーズだろう。 …
-

連載10571回 昭和は遠くなりにけり <5>
(昨日のつづき) 厚生労働省が出している公式の調査統計がいい加減だったという。今夜のテレビが一斉に報じていた。 あらためて驚くことでもない。政府官庁の出す統計資料が適当だったり改竄されていたり…
-

連載10570回 昭和は遠くなりにけり <4>
(昨日のつづき) 夜中、ホテルの窓を打つパラパラという音をきいた。ミゾレが降っているのだろうと思ったが、朝、起きてみるとわずかに雪が残っている。 窓から見る日本海は、低くたれこめた雲の下に文字…
-

連載10569回 昭和は遠くなりにけり <3>
(昨日のつづき) あと数カ月で平成が終る。 しかし、不思議なことに一つの時代が終るという深く重い感慨が胸に迫ってこないのはどういうわけだろう。 昭和が終るときは、そうではなかった。この国全…
-

連載10568回 昭和は遠くなりにけり <2>
(昨日のつづき) いよいよ2019年の仕事はじめだ。 昨夜は『日刊ゲンダイ』『週刊新潮』『サンデー毎日』のコラムを書き、朝までゲラ直し。 きょうは午後から日経新聞出版、中央公論、ほか一社の…
-

連載10567回 昭和は遠くなりにけり <1>
平成最後の松の内も終る。 今年は北陸、東北の豪雪にくらべて、関東地方はあまり雪の降らない正月だった。 <降る雪や 明治は遠くなりにけり> 中村草田男がこの句を詠んだのは、たぶん私が生まれた…
-

連載10566回 今年こそはと毎年思う
平成最後の正月三カ日も過ぎた。 年頭に当り、必ず毎年、「今年こそは」と心に期するものがある。 たとえば、 「必ず午前中に起床しよう」 もう何十年も朝方に寝床に入って、夕方に目覚める生活…
-

連載10565回 新しい年の「マサカ」とは <4>
(昨日のつづき) 今年、最後の原稿である。 毎回、発売前日の深夜にギリギリで入稿する曲芸みたいな仕事を続けながら、事故がおこらなかったのは奇蹟みたいなものだ。 編集部のスタッフの昼夜をいと…
-

連載10564回 新しい年の「マサカ」とは <3>
(昨日のつづき) テレビの健康番組は、あいかわらず過熱気味だ。あいかわらず、というより、最近さらにヒート・アップしてきた感じがある。 先日も、ある地方の大学病院の医師が、神がかり的なアオリで紹…
-

連載10563回 新しい年の「マサカ」とは <2>
(昨日のつづき) 明日のことはわからない。これまで何度となくそう繰り返してきた。 それでも、なお明日のことを考えるのが人間というものだ。来年はこうなる、今年はこうなると、年末、年頭の識者の意見…
-

連載10562回 新しい年の「マサカ」とは <1>
先週、風邪を引いたが、なんとなくうまくやりすごすことができた。年末の忙しい時期だけに、長引かせると大変だと緊張したが、どうやら無事に年をこせそうである。 来年は年号が変る年だ。 平成30年と…
-

連載10561回 早くこいこい、お正月 <5>
(昨日のつづき) 目下、『五木寛之ミュージックボックス』(歌いながら歩いてきた)の編集に追われている。 60年ちかく昔のCM作家時代のコマーシャルソングや、レコード会社で童謡などを書いていた頃…
-

連載10560回 早くこいこい、お正月 <4>
(昨日のつづき) 子供のころ、といっても昭和10年代であるが、それなりに正月は待ち遠しいものだった。 当時は元日に登校することになっていた。学校行事として、祝祭日のセレモニーが行われるのである…