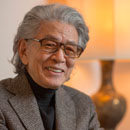五木寛之 流されゆく日々
-

連載10620回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <5>
(昨日のつづき) 昨日、以前から仕事でお世話になっているMさんに、今回のミュージックBOXを差上げた。 Mさんは歌謡曲のみならず、音楽全体に広く識見のある評論家である。手渡したBOXを一見して…
-

連載10619回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <4>
(前回のつづき) そろそろ花見の時期である。まだ寒気のなか、公園の桜の下に場所とりをしている人たちの姿がちらほら見える。 桜は戦時中にも、しばしば歌にうたわれた。 〽万朶の桜か襟の色 …
-

連載10618回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <3>
(昨日のつづき) 私がはじめてレコードを出したのは、たぶん1960年代にさしかかった頃だろうと思う。 はっきりした記憶はないが、当時、TBSラジオで歌の番組を担当していた時期だった。 ちょ…
-

連載10617回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <2>
1960年代にはいった頃、私はCMソングのライターとして仕事をしていた。忙しい日には一日に3つくらいの詞を書いたこともある。 当時はライツという発想がほとんどない時代である。作曲者は名前が明示さ…
-

連載10616回 Mr.ロックンロール追悼 <1>
内田裕也さんの死が報じられた。親しい人でもなく、友人でもなかったが、なんとなくさびしい。故人とは、多少の縁があって、いろいろと思い出すことがあった。 ずいぶん昔に対談をやったことがある。まだお互…
-

連載10615回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <1>
親鸞といえば、なんとなくややこしい思想の持主という感じがする。 北陸のほうでは、親鸞さま、として信仰の対象だが、中興の祖とされる蓮如のほうは、蓮如さんだ。 それでいて知識人のあいだでは、圧倒…
-

連載10614回 樹木希林さんの遺言から <5>
(昨日のつづき) このところ世の中の話題は、まず「健康」。そして次に流行ったのが「老い」という問題だった。 そうなれば、「老い」の後は、「死」ということで、このところ「死」が大話題だ。 し…
-

連載10613回 樹木希林さんの遺言から <4>
(昨日のつづき) 〈103 世の中をダメにするのは老人の跋扈。時が来たら、誇りを持って脇にどくの〉 世の中をダメにするのは青年の失敗ではない、と希林さんは言う。たしかにその通りだ、と、うなずくと…
-

連載10612回 樹木希林さんの遺言から <3>
(昨日のつづき) <065 戦争って、自分のすぐそばの人たちとの戦い> これは卓抜な言葉だ。 私たちは戦争といえば、すぐに米ソの対立とか、第2次世界大戦とかを考える。しかし、戦争は日々、私た…
-

連載10611回 樹木希林さんの遺言から <2>
(昨日のつづき) 『樹木希林 120の遺言』のページをめくると、いたるところで立ち止ってしまう。 ハッとする言葉や、なるほどとうなずくところが随所に出てくるからである。 注目すべきは、この一…
-

連載10610回 樹木希林さんの遺言から <1>
『樹木希林 120の遺言』(宝島社刊)という本を書店で見て、びっくりした。四六判のずしりと重い本格的な本だ。奥付けまで入れると300ページもある。カバーを外してみて、本体の造本がしっかりしていることに…
-

連載10609回 歌いながら歩いてきた <5> ─MYミュージックBOX出来!─
(昨日のつづき) 今度の『ミュージックBOX』には、活字本が2冊はいっている。歌詞と作品についての解説で、アンソロジストの濱田高志さん、アーカイヴァーの鈴木啓之さん、そしてリダークタルの立花莉菜さ…
-

連載10608回 歌いながら歩いてきた <4> ─MYミュージックBOX出来!─
(昨日のつづき) こんどの<ミュージックBOX>は、大きく分けて5部構成になっている。 CDが4枚セットで、DISC1から4まで。 DISC1には『青年は荒野をめざす』から始まって19曲を…
-

連載10607回 歌いながら歩いてきた <3>─MYミュージックBOX出来!─
こんどの『ミュージックBOX』には、私のごく初期の歌の仕事が沢山つまっている。 1950年代後期のCMソングのなかから、何篇か拾って収録したのもその一つだ。私自身もほとんど忘れかけていた半世…
-

連載10606回 歌いながら歩いてきた <2> ─MYミュージックBOX出来!─
(昨日のつづき) 敗戦から引揚までの日々について、語るのは難しい。こんな苦労をいたしました、と同情をそそるような話はいやだし、といって面白おかしく喋るには重すぎる体験だからである。 しかし、そ…
-

連載10604回 養生に定説はあるか <5>
(昨日のつづき) 今日は雨。空気が湿っていると、なんとなく呼吸が楽なような気がする。ふと半世紀以上前の、大学時代の授業のことを思い出した。 ロシア語の教授は、横田瑞穂先生だった。 その日は…
-

連載10603回 養生に定説はあるか <4>
(昨日のつづき) 私自身、いまさまざまな身体上の問題をかかえている。 大半は加齢というさからいがたい自然の結果と言っていい。 人間の体は、ほぼ50年の耐久期限をめやすに作られているらしい。…
-

連載10602回 養生に定説はあるか <3>
(昨日のつづき) <転ばぬ先の杖> などと昔からいう。たしかに転倒というのは高齢者にとって最も危険なことである。 ふだん元気だった人が、何かのはずみで転んで、寝たきりになってそのままという例…
-

連載10601回 養生に定説はあるか <2>
(昨日のつづき) 先日、ある新聞社系の週刊誌に、有名な医学者のかたの記事が連載でのっていた。 その先生は、とくにガンの専門家で、すぐれた実績を残し、ファンも多い有名な方だ。 その記事で、食…
-

連載10600回 養生に定説はあるか <1>
健康法という言葉が、どうしても好きになれない。健康、という表現に首をかしげるところがあるのだ。 健康は良いことだ、人は健康でなければならぬ、といった押しつけを感じるのである。 そこで、ずっと…