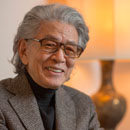五木寛之 流されゆく日々
-

連載10238回 眠れない夜のために <2>
(昨日のつづき) 世の中にはいろんなタイプの人がいる。こと眠りに関しても千差万別だ。 横になったら10秒で大イビキという友人がいた。 「眠れないって、どういうこと?」 と、本気で不思議そ…
-

連載10237回 眠れない夜のために <1>
このところ睡眠のリズムが大幅に狂ってしまって、どうにもならない。 昨年くらいまでは、ほぼ一定のリズムでやってきたのだ。一定のリズムといっても、私の場合は世間の常識からすると、とんでもない生活であ…
-

連載10236回 「健康という病」について <10>
(昨日のつづき) 「健康という病」が、いまこの国を覆っている。 病んでいる人びとが健康を求める気持ちは切実だ。そのことを言っているのではない。「健康になりたい」のではなく、「健康でありたい」風潮…
-

連載10235回 「健康という病」について <9>
(昨日のつづき) 「歩行」。歩くというテーマに関しては、私はこの数十年ずっと関心をもってきた。さまざまな歩行法をためしたり、近代日本人の歩行の歴史的変遷を調べたりして、いっぱしの歩き方の専門家のよう…
-

連載10234回 「健康という病」について <8>
(昨日のつづき) 「整体とか、鍼灸とか、そんなものをためしてみてはいかがですか」 と、親切な編集者がすすめてくれた。 「しかし、ねえ。ああいう民間療法というのは、いまはどこも大繁昌だからなあ。…
-

連載10233回 「健康という病」について <7>
(昨日のつづき) さて、「変形性股関節症」という病名は確定した。なんとなく安心するところがあった。 しかし、とりあえず脚の痛みのほうは、どうすればいいのか。以前は起つとき、坐るとき、歩く際に軽…
-

連載10232回 「健康という病」について <6>
(昨日のつづき) 私が患者として、戦後はじめて訪れた病院の印象は、どうであったか。 もちろんテレビや新聞・雑誌などをとおして、現在の病院の状況はおおむね想像がついていた。 また自分は診察を…
-

連載10231回 「健康という病」について <5>
(昨日のつづき) 私は13歳のときに外地、すなわち旧日本帝国の植民地で敗戦をむかえた。 当時、私たち一家が暮していたのは、現在の北朝鮮である。敗戦と同時に生活が一変した。現地の人びとの旧支配者…
-

連載10230回 「健康という病」について <4>
(昨日のつづき) いまにして思えば、たぶん呼吸器になんらかの異常があったのだろう。息を吸いこむのは普通にできるが、吐くほうが苦しかった。思いきり息を吐いても、十分に吐けずに胸に圧迫感が残るのだ。た…
-

連載10229回 「健康という病」について <3>
(昨日のつづき) 「あなたは健康ですか」 ときかれて、 「ハイ、健康です」 と迷わず即答できる人がどれくらいいるだろうか。 元気盛りの学生時代ならともかく、社会人ともなればなにがしかの…
-

連載10228回 「健康という病」について <2>
(昨日のつづき) 健康という病が蔓延している。最近、つとにそう感じるようになった。 厚労省や医学界では、早期発見、早期治療を国民にすすめるキャンペーンを熱心におこなっている。健康診断の検査の方…
-

連載10227回 「健康という病」について <1>
かつて「健康は命より大事」というジョークがあった。だが今や笑ってはすまされない時代になってきた感じがある。 週刊誌、新聞、月刊誌など、こぞって健康に関する特集の花盛りである。テレビ番組は言うまで…
-

連載10226回 50年代の学生生活 <4>
(昨日のつづき) 1950年代の学生生活をふり返ってみて、懐しいというより不思議な気がしてならない。 その日の食べ物にも困るような暮らしをしながら、けっこう喫茶店とかバーに出かけていたのだ。 …
-

連載10225回 50年代の学生生活 <3>
(昨日のつづき) その頃の大学生は、いまの学生よりもはるかに大人びていたような気がする。 まず大半の学生が煙草を吸っていた。授業中でも、ちょっとひと休みすると教授が煙草に火をつける。当時は大学…
-

連載10224回 50年代の学生生活 <2>
(昨日のつづき) 結局、最初の1年間はほとんど授業に出ることはできなかった。自動的に留年して、1学年下の連中と一緒になった。私が大学の同級生というのは、そのクラスの仲間たちのことである。 当時…
-

連載10223回 50年代の学生生活 <1>
私が大学にはいるために上京したのは、1952年(昭27)の春だった。 1950年にはじまった朝鮮戦争も、38度線をはさんで膠着状態を続けていた時期である。 九州から東京へ来るには、特急で24…
-

連載102222回 一日一食は是か非か <5>
(昨日のつづき) きょうは一食どころか、夜の10時すぎまで食事をしなかった。目覚めるのが夕方になったために、食事の時間がとれなかったのだ。 こういう食生活を続けていて、健康にいいわけがない。し…
-

連載10221回 一日一食は是か非か <4>
(昨日のつづき) 昨日は完全な一日一食だった。途中で何かを口にした記憶もない。 朝、というより午後に起床して、体重を計ってみたら、標準体重より1キロあまり減っていた。 1キロ体重が減ると、…
-

連載10220回 一日一食は是か非か <3>
(昨日のつづき) 規則正しい生活。 ほとんどの健康本が、例外なくそれをすすめている。決まった時間の食事。決まった時間の就寝。そして早起き。 私の友人の一人に、絵に描いたような健康志向の作家…
-

連載10219回 一日一食は是か非か <2>
(昨日のつづき) 食事のとり方については、永年いろんな説が錯綜している。 一般に多いのは、一日三食説だ。ことに朝食を重視する論者が多い。こういう人はほとんど早寝早起き説である。ある意味で道徳的…