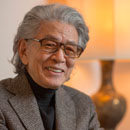五木寛之 流されゆく日々
-

連載10642回 高齢者と車の運転 <4>
(昨日のつづき) きょうもまた何件かの交通事故のニュースが流れた。不条理な死に見舞われた被害者の家族の気持ちは察するにあまりある。 昨日の話の続きだが、戦時中の航空少年は、戦後、禁じられた空の…
-

連載10641回 高齢者と車の運転 <3>
(昨日のつづき) そんなわけで、60歳を過ぎた頃から、いつ運転から撤退しようかと考えていた。 もちろん、各方面から指摘されたように、自動車を自分で運転せずに生活できるという事情もあった。 …
-

連載10640回 高齢者と車の運転 <2>
(昨日のつづき) 私が自分の老化を感じはじめたのは、50代の後半からだった。60歳をこえると、あきらかに運動機能の衰えを自覚するようになった。 たとえば、よく物を落とすことがある。ふだんなに気…
-

連載10639回 高齢者と車の運転 <1>
高齢のドライバーによる悲惨な事故がおきた。言葉もない。 愛憎のもつれとか、金がからむ事件とか、そういうケースとは全然ちがう事故である。突然に降りかかる事故ほど不条理なものはない。 それにして…
-

連載10638回 三日見ぬまの桜かな <5>
(昨日のつづき) ノートルダム寺院が炎上する写真を見て、なにか一つの時代が終る感じがした。シャンゼリゼーの伝統あるカフェ、ル・フーケも先日のデモで焼けた。いろんな小説や映画に登場する場所が被害にあ…
-

連載10637回 三日見ぬまの桜かな <4>
(昨日のつづき) 「三日見ぬまの桜」 などと気軽に使ってきたが、実のところその言葉の出所を知らなかった。お恥しい限りである。 今回、あちこちで「三日見ぬ間の桜」と書いたり喋ったりする機会が多…
-

連載10636回 三日見ぬまの桜かな <3>
(昨日のつづき) タクシーに乗って、支払いをしようとしたら、 「現金ですか?」 と、きかれた。最近はこういうことが多くなったような気がする。それだけカードで払う人が多くなったのだろう。 …
-

連載10635回 三日見ぬまの桜かな <2>
(昨日のつづき) 昨夜は久しぶりに完全徹夜した。 『中央公論』に連載中の「一期一会の人びと」の原稿が難航して、1週間ちかくおくれてしまったのだ。 最近、つとめて締め切りは厳守するようにしてい…
-

連載10634回 三日見ぬまの桜かな <1>
13日に、北九州市民文化大学の講演で小倉にいった。 北九州市となって久しいが、私たち昭和世代の人間にとっては、なんとなく小倉のほうがなじみやすい。 北九州市民文化大学は、平成元年に開校したと…
-

連載10633回 私が父から相続したもの <5>
(昨日のつづき) 師範学校を卒業して、父親が最初に勤めたのは、たぶん福岡県の筑後地方の小学校であったにちがいない。 私はその辺のことをちゃんと相続していないので推測するしかないのである。 …
-

連載10632回 私が父から相続したもの <4>
(昨日のつづき) まあ、そんなわけで、父親は九州辺地の農民の子弟から、いわゆる「亜インテリ」の仲間入りをした、と言っていいだろう。 私はこの「亜インテリ」という表現が嫌いである。本格的知識人、…
-

連載10631回 私が父から相続したもの <3>
(昨日のつづき) 父親のことを書きつつ、はたと当惑した。 彼はいったいいつ頃に生まれたのだろうか。はっきり言って、私は父親の正確な生年月日を知らない。戸籍を見れば、すぐにわかることだ。以前、何…
-

連載10630回 私が父から相続したもの <2>
(昨日のつづき) 私の父親は九州の山村の農家に、非長子として生まれた。山あいの集落であるから、農地も限られている。 網野善彦のいう<百姓>という典型的な農家だった。 私も引揚後、その父の実…
-

連載10629回 私が父から相続したもの <1>
相続について再び書く。 くり返しになるが、私は父親から「形あるもの」を、まったく相続しなかった。 その日暮しの引揚者であるから、土地、家屋などはもちろんない。資産といえるものを全く引き継ぐこ…
-

連載10627回 令和について考える <3>
(昨日のつづき) 今回の元号選定にあたっては、国文学者であり、万葉集研究の第一人者でもある中西進さんの提言が大きかったと伝えられている。 中西さんは、奈良県明日香村の「万葉文化館」の初代館長(…
-

連載10626回 令和について考える <2>
(昨日のつづき) 思えば昭和は「桜の時代」であった。 〽見事 散りましょ 国のため という歌は、今でも耳の奥に残っている。 〽咲いた花なら 散るのは覚悟 という例の歌だ。固苦しい軍歌よ…
-

連載10625回 令和について考える <1>
「令和」と年号が変って、マスコミも国民も大騒ぎである。号外を奪い合って転倒する姿までニュースで報道された。 「あ、そう」 と、冷淡な国民など、一人もいないような印象だが、私の周辺では格別な興奮は…
-

連載10623回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <8>
(昨日のつづき) 初期のころのことを良く知っている関係者は、私のことを今でも「のぶさん」などと呼ぶ。CMソングだけでなく、NHKの番組なども「のぶ ひろし」名義でやっていたからだ。 クラウン時…
-

連載10622回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <7>
(昨日のつづき) 自称「海山稼ぐ者」である私は、これまでずっと雑多な仕事をして生きてきた。 こんど発売になった『歌いながら歩いてきた』(ミュージックBOX/日本コロムビア)は、その雑多な仕事の…
-

連載10621回 歌は生きた年代誌(クロニクル) <6>
(昨日のつづき) 今回の『歌いながら歩いてきた』に収めたCDの1枚目のトップは、ザ・フォーク・クルセダーズの『青年は荒野をめざす』だ。 これに対してカウンター・ソングというわけではないがDIS…