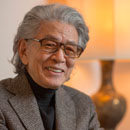五木寛之 流されゆく日々
-

連載12176回 昭和落ち穂拾い <1>
最近、<ことば恐怖症>にかかっている。 自分にとっては、ごく普通の物言いが、ときとして若い世代に通じないことがしばしばあるからだ。 「それ、なんですか?」 と、けげんそうな顔できいてくれれ…
-

連載12175回 孤児と棄児の間には <4>
(昨日のつづき) <戦災孤児>とは、家族兄弟を戦災で失った子供である。 <棄児>とは、家族兄弟に置き去りにされた子供である。 両者は似ているように思われるが、そうではない。 母親がわが子を…
-

連載12174回 孤児と棄児の間には <3>
(昨日のつづき) <戦災孤児>という言葉がよく使われた時代があった。 前の戦争で両親、家族を失った子供たちのことである。施設に収容される子供たちもいたが、勝手に独りで焼跡に生きていく少年たちも少…
-

連載12173回 孤児と棄児の間には <2>
(昨日のつづき) 旧満州から北朝鮮に逃れてきた難民たちの姿は、平壌に取り残された在留日本人の比ではなかった。 連日のようにそれらの人々が集団で平壌の街に流入する。その有様は家を接収され、難民化…
-

連載12172回 孤児と棄児の間には <1>
戦後80年。 <戦災孤児>という言葉も、ほとんど聞かなくなった令和7年の夏である。 しかし戦後の一時期は、<孤児>が世の中にあふれていたのだ。空襲で、家族、縁者をなくした子供たちが、上野の地下…
-

連載12171回 日本社会の弱点
どうしてこうなんだろう、と思うことが多々ある。 先日、ある会に出席した。 東京都内の、れっきとしたシティ・ホテルのホールでの催しだった。 会の最初から気になっていたのだが、会場の音響シス…
-

連載12170回 戦前、戦中、戦後
昭和20年8月に戦争が終った。この国の歴史はじまって以来の出来事だった。 それまでと世の中が一変した。いや、正確にいうと変ったものと、変らなかったものとがある。 変ったものについては、ご覧の…
-

連載12169回 遠い記憶の断片 ──桑港への使節団を見送る──
<桑港>と書いてサンフランシスコと読む。昔は新聞にも<桑港>とか<紐育>とかいう見出しが出ていたものだが、最近は見なくなった。 私は昭和27年(1952)に九州から上京して大学に入った。大学に顔を…
-

連載12168回 ペンと杖の日々
私がはじめて文章を書くことでお金をもらったのは、大学へはいって4、5年たった頃だったと思う。 当時、私は学費未納の常連として、文学部校舎の廊下に名前が貼りだされていた。アルバイトでなんとか生活は…
-

連載12167回 長篇を読む意味 ──森詠「川は流れる」を読む──
最近、長篇小説を読む機会が少くなった。 昔は見栄で長篇小説と取り組む傾向が文学青年のあいだにもあったのだ。 私も『戦争と平和』を、夏休み中に読むぞと気おって部屋に積みあげたこともあったが、遂…
-

連載12166回 口笛を吹きながら <5>
(昨日のつづき) 秋田へいってきた。 秋田魁新報と秋田県立大学が共催する<生涯学習プログラム>の公開講演会で、講演というか、短いお喋りをするためである。 短いというのは講演の時間が1時間と…
-

連載12165回 口笛を吹きながら <4>
(昨日のつづき) 1173年に生まれた親鸞については、さまざまな文献があるが、本当のところはよくわからない。 定説はもちろんある。権威ある学者の研究もあるし、とほうもない仮説もないではない。 …
-

連載12164回 口笛を吹きながら <3>
(昨日のつづき) 人はだれでも、時として夜中に何度か目が覚めることがあるものです。 運動するのと同じように、眠るにもエネルギーが必要であるらしい。未だ夜明けには遠い深夜にひとり目覚めて、あれこ…
-

連載12163回 口笛を吹きながら <2>
(昨日のつづき) <人生は短く 芸術は長し> などといいますが、実際には人生も決して短いものではありません。 桜の花のように、パッと咲いてパッと散ることが国民の生き甲斐のようにいわれた戦前、…
-

連載12162回 口笛を吹きながら <1>
人が長生きするようになったことは、人間にとってはたして幸せなことなのだろうか、とふと考えることがあります。 最近の統計では、男性の平均寿命は、およそ81歳。女性が87歳となっています。 女性…
-

連載12161回 いい加減な生き方 <5>
(昨日のつづき) 文明は確かに進歩した。 AIの登場など、かつては想像もできなかった文明の利器の登場である。 機械と人間、という究極の問いが今、私たちにつきつけられているのだ。 人生相…
-

連載12160回 いい加減な生き方 <4>
(昨日のつづき) 戦争というのは、やっている最中が問題なのではない。 戦後、すなわち戦争が終った後が大変なのだ。 戦後80年という。区切りのいい時期ではあるが、80年たっても戦争は本当に終…
-

連載12159回 いい加減な生き方 <3>
(昨日のつづき) きょうは日本経済新聞のインターヴュー。 長嶋フィーバーが一段落したと思ったら、こんどは戦後80年とかで、1945年の夏の記憶を総ざらい。 なにしろ当時のことを思い出して語…
-

連載12158回 いい加減な生き方 <2>
(昨日のつづき) 人はどう生きるべきか。 時代を超えて、すべての人間はそのことを考える。 考えることが苦手な人間でも、折りにふれて自分の生き方について思うことはあるだろう。 人はさまざ…
-

連載12157回 いい加減な生き方 <1>
なにごとにつけても、私はいい加減な人間だ、と、つくづく思うことがある。 しかし、いい加減、ということは、そもそもがいい加減な表現なのだ。 そこには2つの意味があるので厄介なのだ。たとえば「い…