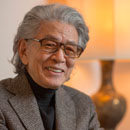五木寛之 流されゆく日々
-

連載12216回 町場の昭和歌謡談義 <4>
(昨日のつづき) 横山剣さん、前田和男さん、齋藤孝さんと3人続いたところで、トリはタブレット純さんである。 この人はまことに才筆、というか、文章がしっかりしている。歌い手さんのタレント本は星の…
-

連載12215回 町場の昭和歌謡談義──『昭和歌謡界隈の歩き方』── <3>
(昨日のつづき) 齋藤孝さんの『昭和歌謡界隈の歩き方』、横山剣さんの『昭和歌謡イイネ!』とビッグネームが並んだところで、異色の歌謡論を紹介しよう。 前田和男著『「カチューシャ」とウクライナ戦争…
-

連載12214回 街場の昭和歌謡談義──『昭和歌謡界隈の歩き方』 <2>
(昨日のつづき) 横山剣さんの昭和歌謡回顧に続いて、齋藤孝さんの『昭和歌謡界隈の歩き方』(白秋社刊)。 この<界隈>という表現が「イイネ!」。つい横山剣さんの口調がうつってしまった。 <人生…
-

連載12213回 街場の昭和歌謡談義 <1>
このところ或る共通の雰囲気をもった本が目立っている。造本、装丁、文体などに、どこか共通した雰囲気のある四六判、ソフトカバーの新刊本である。 気軽に手にとって立ち読みもできそうな感じの本だ。カバー…
-

連載12212回 私の街場の養生論 <4>
(昨日のつづき) <舌の運動>につづいて大事なのは<耳>だ。<語る>ためには<聴く>ことが前提である。<よく聴く者>は、<よく語る者>。 出すためには入れることが不可欠だ。 年齢を重ねるにつ…
-

連載12211回 私の街場の養生論 <3>
(昨日のつづき) まず舌先を思いきり突き出してみる。 その舌先を、水平に開いた口の左右の端に軽くタッチするように左右に軽快に動かす。 最初はギコチナクしか動かなくても、慣れれば素早く左右に…
-

連載12210回 私の街場の養生論 <2>
(昨日のつづき) 私は自慢ではないが、ズボラな人間である。 謙遜で言っているのではない。 ときには同じパンツを1週間ずっと履きつづけていることもある。 <面倒くさい> というのが私の…
-

連載12209回 私の街場の養生論 <1>
私の「座右の書」の一冊に、多田富雄さんの『免疫の意味論』がある。(といっても、常に雑然と枕元に積みあげてあるだけだから、「座右」というより「枕前の書」というべきかもしれないが) 多田さんとは、金…
-

連載12208回 好奇心のままに <3>
(昨日のつづき) 敗戦で一変した少年の思想だが、それにかわる新しい発想は現れてこなかった。 これが内地(日本本土)であれば、少年といえども新聞、雑誌、本などで新しい文化への展望を見出すこともで…
-

連載12207回 好奇心のままに <2>
(昨日のつづき) <あすはどうなるかわからない> と、いうのは、子供の頃からの私の固定観念である。 なぜそんな観念にとりつかれたかはわからないが、中学1年生のときの敗戦をもって、その観念は私…
-

連載12206回 好奇心のままに <1>
先月末に93歳の誕生日をむかえた。 何人かのかたから、お祝いの品や花などをいただいた。ありがとうございます、と紙面を借りてお礼を申し上げておく。 しかし、後期高齢者が、さらにその上に歳を重ね…
-

連載12205回 金沢文芸館のこと <5>
(昨日のつづき) 金沢文芸館内で現在開催中の<五木寛之文庫>の今回の展示テーマは、<活字とラジオのあいだには>。 ちょっと一般の作家展ではお目にかかれない企画である。 不肖、私のラジオのキ…
-

連載12204回 金沢文芸館のこと <4>
(前回のつづき) こうして金沢文芸館の2階に、ささやかな〈五木寛之文庫>がオープンした。 以来、今日までさまざまな企画展が開催され続けてきた。<陳列品の展示館>ではなく、その時代ごとの生きた時…
-

連載12203回 金沢文芸館のこと <3>
(昨日のつづき) しかし、どうせその手の施設をスタートさせるのならば、市内の一角にひっそりと立つ古い建物の片隅に、ささやかなコーナーを作るというアイディアに、心惹かれるところがあったのも事実である…
-

連載12202回 金沢文芸館のこと <2>
(昨日のつづき) 前回の原稿で、金沢のことを<第3のふるさと>と書いたのは誤りで、<第4のふるさと>というのが正しい。 生まれた福岡が<第1のふるさと> 育った朝鮮半島が<第2のふるさと>…
-

連載12201回 金沢文芸館のこと <1>
金沢へきた。 雨の多い土地柄だが、きょうは降ってはいない。 午後、尾張町の金沢文芸館でテレビ金沢の取材。金沢文芸館は今年で創立20周年を迎える。 地味な存在ながら、地域文芸運動の基点とし…
-

連載12200回 中世のうたごえ <12>
(昨日のつづき) 法然一門の若手アイドルともいうべき美少年グループの人気が沸騰し、彼らが催す念仏会が熱狂的な人気を集め、念仏高唱の声が巷にあふれることは、法然一門にとっては危険なことです。念仏だけ…
-

連載12199回 中世のうたごえ <11>
(昨日のつづき) 平安時代の<うたごえ>はともかく、現代の<うたごえ>はどうなっているのか。 昭和100年、戦後80年ということで、さまざまな話題がメディアにあふれました。ことに<昭和歌謡>と…
-

連載12198回 中世のうたごえ <10>
(昨日のつづき) 旧仏教のセンターである奈良の大寺はもちろんのこと、比叡山も、その他の寺々も、こぞって念仏の流行を批判しました。 <悪人もすくわれる>どころではなく、苦しんでいるアンタたちこそ浄…
-

連載12197回 中世のうたごえ <9>
(昨日のつづき) 新しい念仏で大フィーバーをおこした法然の<口称念仏>ですが、それが社会現象となるには、さまざまな要素があります。 法然をしたって集ってくる門下には、多くの僧がいました。古い寺…