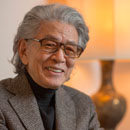五木寛之 流されゆく日々
-

連載12196回 中世のうたごえ <8>
(前回のつづき) 当時の比叡山は<鎮護国家>の象徴として、その権威は並ぶものなき高貴な山でした。しかも仏教の研鑽だけでなく、天文学、言語学など、あらゆる分野の学問研究においてトップレベルの総合大学…
-

連載12195回 中世のうたごえ <7>
(前回のつづき) 仏教にしても、キリスト教にしても、イスラム教にしても、絶対的信仰というものを土台にして成り立つ宗教です。 その<絶対的信仰>は、どこからもたらされるのか。 たぶん、それは…
-

連載12194回 中世のうたごえ <6>
(昨日のつづき) それまで、われら仏に見捨てられていた者たちにも、救われる道がある、という驚きと感動から、一つの歌がうたわれます。 〽弥陀の救いぞたのもしき 十悪五逆の悪人も 南無阿弥陀仏と唱れ…
-

連載12193回 中世のうたごえ <5>
(昨日のつづき) みずからを<海山稼ぐ者>と卑下している人々に対して、その固定観念を笑い飛ばしたのが高野山を降りた名僧、法然でした。 <仏は差別なく、すべての人々を救う> と、彼は説いたので…
-

連載12192回 中世のうたごえ <4>
(昨日のつづき) 真宗の念仏について、ひとつの誤解があるようです。 それは「南無阿弥陀仏」という浄土系の念仏が農民や底辺の民衆から支持されて広まったというイメージです。 「悪人往生」の思想が…
-

連載12191回 中世のうたごえ <3>
(前回のつづき) 地獄、極楽、というイメージが広く人々のあいだに定着するのもその頃です。 <極楽>のすばらしさは、さまざまに語られますが、それ以上に当時の人々に強烈なインパクトをあたえたのは<地…
-

連載12190回 中世のうたごえ <2>
(昨日のつづき) 今様というのは、読んで字の通り「いまどきの」「当世風の」という意味の歌謡です。 まあ、平安時代のニューミュージックといってもいいでしょう。 当初のものは10世紀後半あたり…
-

連載12189回 中世のうたごえ <1>
むかしの時代劇というか、チャンバラ映画に、こんなシーンがよくありました。 暗い川ぞいの土手の道。 月もおぼろに、どことなく不隠な気配のなかを、一人の浪人ふうの男が歩いている。 突然、草陰…
-

連載12188回 昭和の不可触世界 <3>
(昨日のつづき) <売春防止法>が成立したのは1956年。実際に施行されたのは、翌年からである。 新宿2丁目、その他全国各所で『蛍の光』が合唱された。 しかし、公然と非公然の形は異なっていて…
-

連載12187回 昭和の不可触世界 <2>
(昨日のつづき) 大学生のころ、永井荷風の『濹東綺譚』を読んで、その作品の舞台になった玉の井のあたりを歩いたことがある。 戦後10年ちかくたっても、どこかに物語りの舞台となった街の風情は、色濃…
-

連載12186回 昭和の不可触世界 <1>
<昭和百年>も、そろそろ種切れのようだ。 これまでさんざん読まされてきたなかで、なぜか書き手があまり触れようとしない部分があるのはなぜだろう。 それは「昭和の売春」世界のことだ。 はっきり…
-

連載12185回 昭和落ち穂拾い <10>
(昨日のつづき) <昭和>と、ひとくちに言うけれど、昭和は長い。しかも戦前と戦中、戦後ではまったくちがう。できれば<戦前昭和><戦中昭和><戦後昭和>と、はっきり3つに分けて語ったほうがいいのではあ…
-

連載12184回 昭和落ち穂拾い <9>
(昨日のつづき) 昭和の頃は、イラストレーターなどという呼びかたはなかった。<挿絵画家>というのが一般的だった。 当時の物語り性のつよい少年読物を、さらに魅力的にドレスアップするのも挿絵画家の…
-

連載12183回 昭和落ち穂拾い <8>
(昨日のつづき) 「昭和歌謡」のブームは、まだ衰えてはいないようだ。 このところ新聞の一ページ広告に、あいかわらず昭和の流行歌のアルバム・全集のたぐいの広告が目立つ。 <流行歌>という言葉には…
-

連載12182回 昭和落ち穂拾い <7>
(昨日のつづき) 上級生による集団暴行事件で、ある出場校が甲子園を途中辞退したことが大きな話題となっていた。 私は小学校(国民学校)のときも、中学生のときも、同じ校内の先輩、同級生に暴力を受け…
-

連載12181回 昭和落ち穂拾い <6>
(前回のつづき) 父が願いかなって、大都市の学校に奉職できたのは、私が小学校に入る前年ぐらいの年だったと思う。いくら思い返しても、その辺の正確な時期が思い出せないのだ。 私たち一家は、母の夢見…
-

連載12180回 昭和落ち穂拾い <5>
(昨日のつづき) 8月に読んだ本。 『十四歳<フォーティーン>満州開拓村からの帰還』/澤地久枝著/集英社新書。8月に必読の一冊。 『なぜ日本人は間違えたのか 真説・昭和100年と戦後80年』/…
-

連載12179回 昭和落ち穂拾い <4>
(昨日のつづき) 私の父親は、北九州の小倉師範学校の出身だった。 母親は福岡市の福岡女子師範学校を出て、筑後の村の小学校教師として勤めていたらしい。 らしい、というのは、私が母と早く別れた…
-

連載12178回 昭和落ち穂拾い <3>
(昨日のつづき) 私が幼なかった頃にいた村の名前を思い出そうとするのだが、どうしても記憶がよみがえってこない。 前回、書いたようにその村には、日本人は私たち家族と駐在所の警官だけだった。 …
-

連載12177回 昭和落ち穂拾い <2>
(昨日のつづき) かつてわが国には<内地>と<外地>という2つの地域があった。 一般的には、古来からの日本列島のことを<内地>と呼び、明治以来、日本が領有した国土を外地と称した。朝鮮、台湾、樺…