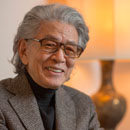五木寛之 流されゆく日々
-

連載11217回 先週読んだ本の中から <5>
(昨日のつづき) 先週読んだ本の中で、最も分厚く、最も重かったのが『新・日露異色の群像30』(生活ジャーナル刊)だ。 <――文化・相互理解に尽くした人々>とサブタイトルが付いている。一体どんな人…
-

連載11216回 先週読んだ本の中から <4>
(昨日のつづき) 中井正一の『日本の美 』(中公文庫)と、文遊社から出た『阿部薫2020-僕の前に誰もいなかった』を交互に読んだ。 かたや本体価格820円の文庫本。かたや本体2700円のずしり…
-

連載11215回 先週読んだ本の中から <3>
(昨日のつづき) さて、今井雅晴さんの『親鸞の伝承と史実』について。 親鸞本、という言い方は失礼だが、およそわが国の仏教関係図書の中で最も数が多いのは、親鸞その人についての本ではあるまいか。 …
-

連載11214回 先週読んだ本の中から <2>
(昨日のつづき) この1週間ほどのあいだに読んだ本を挙げると、おおむねこんなところだろう。 『作家は時代の神経である』(高村薫著/毎日新聞出版刊) 『日本の美』(中井正一著/中公文庫) 『新…
-

連載11213回 先週読んだ本の中から <1>
〽どこまで続くヌカルミぞ である。こう書いても若い読者諸君(70歳以下)には、何の感慨もないことだろう。昭和前期の戦争中に日本国民がひとしく熱唱した戦時歌謡の一節である。はたして中国との戦争は、そ…
-

連載11212回 仏の顔も三度、とは? <5>
(昨日のつづき) 東海道新幹線の岡山から新横浜までの車中で、私の車両に乗っていた客は9人だった。私以外は8人である。 緊急事態宣言は、ある程度の効果があるのだろう。どの車両も乗客は少いようだ。…
-

連載11211回 仏の顔も三度、とは? <4>
(昨日のつづき) 1泊で岡山へ行ってきた。緊急事態宣言のさなかに県をまたいで移動するのは気が引けるが、2回目のワクチン接種も終えて体調も悪くないことだし、ちゃんとマスクをしていけば大丈夫だろうと、…
-

連載11210回 仏の顔も三度、とは? <3>
(昨日のつづき) 空の気配はすでに秋である。 空を眺めることなどめったにないが、ステイホームとあって、窓からぼんやり雲の行方を確かめたりする時もないではない。 考えてみると、空の雲の行方を…
-

連載11209回 仏の顔も三度、とは? <2>
(昨日のつづき) 仏の顔も三度どころか、緊急事態宣言はすでに四度目である。 緊急事態というからには、もう少し緊張感が欲しいところだが、世間は一向にピリッとしていない。 それどころか、コロナ…
-

連載11208回 仏の顔も三度、とは? <1>
<入院が できたと聞いて おめでとう> 誰の作か忘れてしまったが、思わず笑ってしまった。さすがに川柳は乱世の芸術である。 後世の人は、たぶん、この句を聞いても何のことだか判らないのではあるまい…
-

連載11207回 30年前の文章から <10>
(昨日のつづき) 古い本や雑誌を捨てなければならない。 それなりに風格のある書物や印刷物なら、本人が死んだ後でも、なにかの役に立つかもしれないが、ただ雑然と手もとにあった本や雑誌はただの場所ふ…
-

連載11206回 30年前の文章から <9>
(昨日のつづき) 車の色に関する感覚がドイツ車もはんぱではない。私も色に関してはこだわるほうだった。私が使っていたポルシェは、<シエナ・ブラウン・メタリック>だった。 ポルシェはなんとなくメタ…
-

連載11205回 30年前の文章から <8>
(昨日のつづき) <(続)監督のリドリー・スコットというのは、どうやらフランス人ではないらしいから、やはりお国柄が出てしまったのだろうか。 コンラッドの母国は、有名なポーランド騎兵隊の国、ポーラ…
-

連載11204回 30年前の文章から <7>
(昨日のつづき) 89回ルマン耐久レースでトヨタ・チームが優勝した。小林可夢偉の乗る7号車である。トヨタはこれでルマン4連覇。ルマンで勝つということは、大したことなのだ。 それでもEUは203…
-

連載11203回 30年前の文章から <6>
(前回のつづき) クルマの話にどうして<グミ・キャンデー>が出てくるんだろうと、不思議に思われた読者もいることだろう。まあ、続きを読んでください。 或る席でグミをすすめられて口にしてから、しば…
-

連載11202回 30年前の文章から <5>
(昨日のつづき) 今回も『30年前の文章から』の続きである。 このところ気の滅入るニュースばかりで、ステイ・ホームの日々もすこぶる鬱々たるものだ。30年前の虚栄の余香を思い返してみるのも悪くな…
-

連載11201回 30年前の文章から <4>
(昨日のつづき) 91年6月第2週の『流されゆく日々』には、こんなことを書いている。 『ドイツ的なるものの謎』という文章である。 (No3828回~3835回) <(前略)ドイツ的なもの。 …
-

連載11200回 30年前の文章から <3>
(昨日のつづき) 30年前といえば、1991年、私が50代後半の時期である。 当時はまだ自分で車を運転していた。その頃の私の道楽といえばもっぱら車だった。しかし私はこれまで一度も超高価なスーパ…
-

連載11199回 30年前の文章から <2>
(昨日のつづき) ちょうど30年前の『流されゆく日々』の文章の中から、いくつかのフレーズを拾いあげてみよう。<予測不可能な時代に>というのが、その週のコラムのタイトルだ。 ’91年8月後半に掲…
-

連載11198回 30年前の文章から <1>
今日、敗戦の日。8月15日という日付けが、1年ごとに色褪せていく。新聞の扱いも心なしか控え目である。 戦後70余年も過ぎれば当然だろう。いまはデジタルトランスフォーメイションの時代なのだ。<戦争…