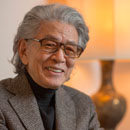五木寛之 流されゆく日々
-

連載10057回 エロ・テロ・ナンセンスの時代 <3>
(昨日のつづき) きのうペンクラブでした短いスピーチの続き。 日本ペンクラブが発足したのは、1935年(昭10年)の秋である。私が生まれたのが1932年だから、3年後のことだ。いわば戦前の時代…
-

連載10056回 エロ・テロ・ナンセンスの時代 <2>
(昨日のつづき) きょうは夕方から如水会館へ。 日本ペンクラブの催しで、短いスピーチを頼まれていたのだ。 私はダラダラと長い時間お喋りをするのが向いているタイプで、短い話は苦手である。15…
-

連載10055回 エロ・テロ・ナンセンスの時代 <1>
カストロ死去のニュースが世界中を駆けめぐった。 20世紀がこれで完全に終ったということだろう。90歳。天寿をまっとうした革命家というのはめずらしい。 暗殺計画は、数百回におよぶといわれている…
-

連載10054回 戦前 戦中の短い記憶 <4>
(昨日のつづき) 小学生、そして中学に入学した時期、どんな本を読んでいたのかを思い出してみる。 じつに雑多な読書だった。いや、読書というほどのものでもない。手当りしだいに活字をあさっていた、と…
-

連載10053回 戦前 戦中の短い記憶 <3>
(前回のつづき) いわゆる昭和ヒトケタ派の連中が次々と退場して、なんとなく淋しくなった。後に続く世代にとってはウットウしい存在だったかもしれない。しかし、彼らがいなくなったことで、現代史が年表でし…
-

連載10052回 戦前 戦中の短い記憶 <2>
(昨日のつづき) きょう毎日新聞のインターヴューを受けたときに、鈴木さんから意外な事を教えられた。 私が『とらわれない』(新潮新書)の中で触れていた戦時中の国民歌謡の件である。 〽歩け 歩け…
-

連載10051回 戦前 戦中の短い記憶 <1>
私はタンゴが好きだった。いまでもタンゴの音色をきくと、血が騒ぐところがある。 タンゴという音楽が全世界に流行したのは、ごく短い年月だった。1920年代半ばから30年代の前半といっていいのではある…
-

連載10050回 「新国家主義」の幕開き <5>
(昨日のつづき) 人間は「忘れる動物」である。 これだけは絶対に忘れまいと心に誓っていても、10年もたてばたちまち忘れてしまう。しかし、もし人間が決して忘れることをしなかったなら、たぶん生きて…
-

連載10049回 「新国家主義」の幕開き <4>
(昨日のつづき) 民族主義と国家主義とはちがう。しかし、紙一重のところで両者は接しているところがある。 国民国家がグローバルな市場国家となり、その反動として体制国家が登場する。グローバリゼイシ…
-

連載10048回 「新国家主義」の幕開き <3>
(昨日のつづき) あたりはしんと静まり返っている。ひげの男たちが肩を組み合ったり、頬を寄せあって舞台をみつめている姿が見える。 「いったいどういうショウをやるんですか」 と、スタッフの一人が…
-

連載10047回 「新国家主義」の幕開き <2>
(昨日のつづき) 勝手に「新国家主義」などと呼んだ風潮は、すでに数十年前から世界の各地できざしていた流れである。それが最近、急激にあらわになっただけのことだ。 かなり昔のことになるが、『燃える…
-

連載10046回 「新国家主義」の幕開き <1>
トランプがアメリカ大統領になる。正直に言って、なんだかんだといっても、結局、クリントンだろうと思っていたのだ。メディアもこぞってクリントンを推した。反トランプの声も大きい。そんな流れの中で、最後はト…
-

連載10045回 金沢はめずらしく晴れ <5>
(昨日のつづき) ギックリ腰は3日目を迎えても、まだ立去ってはくれない。魔女の一撃とよく言うが、原因はわかっている。机の前に長時間坐り続けたことの報いである。左脚をかばい過ぎて、腰に負担がかかった…
-

連載10044回 金沢はめずらしく晴れ <4>
(昨日のつづき) 今朝、起きたらギックリ腰がさらに悪化している。ベッドから起きあがれない位の痛みである。 スケジュール表では、本日、夕方7時から新潮社の本社ホールで新潮講座の講演が予定されてい…
-

連載10043回 金沢はめずらしく晴れ <3>
(昨日のつづき) 金沢から帰ってきた日の夜から、しきりに腰が痛みだした。 2時間半の新幹線とはいえ、ずっと坐りっぱなしだったのが良くなかったのかもしれない。 人類は坐ることで滅亡するという…
-

連載10042回 金沢はめずらしく晴れ <2>
(昨日のつづき) 金沢から帰ってきて、一日おいた今日、夕方からNHKの番組の仕事でロバート・キャンベルさんと対談。 キャンベルさんとは初対面だが、以前、国文学系の雑誌でわが国の漢詩文に関する意…
-

連載10041回 金沢はめずらしく晴れ <1>
泉鏡花文学賞の授賞式に参加するため、北陸新幹線で金沢へ。 あれこれと雑用が重なっていて、なかなかスケジュール調整がむずかしい。一時は朝の新幹線で金沢へ行き、授賞式を終えたあと最終便で帰ってくるこ…
-

連載10040回 昭和ヒトケタ派の残影 <4>
(前回のつづき) しかし、昭和ヒトケタといっても、実は百人百様である。同じ時代を共有していながら、驚くほどその周囲の状況は異るのだ。 私より1、2歳年上のある現代史家は、戦時中、父親から「この…
-

連載10039回 昭和ヒトケタ派の残影 <3>
(昨日のつづき) 前回、高井有一さんと会ったのは、やはり坪田譲治文学賞の選考の席でだった。 そのとき、高井さんは、椅子に坐ったり立ったりするのが、かなり不自由な様子だった。 「では、お先に失…
-

連載10038回 昭和ヒトケタ派の残影 <2>
(昨日のつづき) いま、この原稿を公衆電話のあるコーナーで立ったまま書いている。仕事の都合で、部屋へもどって書く時間がなくなってしまったのだ。四十数年、こんなふうにしてこのコラムを書き続けてきた。こ…