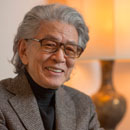五木寛之 流されゆく日々
-

連載10280回 「孤独のすすめ」補稿 <1>
世の中はわからないものである。政治の世界が「一寸先は闇」だとは知っていた。 しかし、実際にはすべての事が、予測どおりには動かない。こと出版の世界もそうだ。 考えてみれば、すでに60年以上もメ…
-

連載10279回 健康病という病い <5>
(昨日のつづき) 目を覚ますと、すぐに時計を見る人がいる。昨夜、何時間眠れたかが気になるのだ。 睡眠時間は5時間でよい、という情報もある。要するに良質の睡眠がとれたかどうかが問題だという。それ…
-

連載10278回 健康病という病 <4>
(昨日のつづき) ヘルス情報からヘルシー情報へ。 この怒濤のような健康情報の物量は、最近ほとんど全ニュースの中心となった感がある。 しかも、その内容の多様性は呆れるくらいのものだ。正反対の…
-

連載10277回 健康病という病 <3>
(昨日のつづき) 『日刊ゲンダイ』というのは、創刊時からずっと一貫して傾向的な夕刊だった。 たとえば政治だけでなく、すべてにわたって反体制、反権力という片寄りがある。むかし巨人が圧倒的に強かった…
-

連載10276回 健康病という病 <2>
(昨日のつづき) 私のひそかな趣味のひとつは、入浴である。入浴というとバスタブにつかり、体を洗ったり髪を洗ったりすることを想像されるだろうが、私の場合はそうではない。 ややぬる目の湯に、体を浸…
-

連載10275回 健康病という病 <1>
私は自分の健康に関しては、かなり無頓着なほうだ。無頓着というより非常識といったほうがいいかもしれない。 私はこれまで健康診断とか検査とかいうものを、戦後70年いちども受けたことがなかった。また、…
-

連載10274回 健康というストレス <5>
(昨日のつづき) がん発生の主なる原因は、ストレスであるという。がんについて本当のところは、まだ100パーセント明確にわかっていないのだ。さまざまな科学的、医学的推論はなされていても、完全に解明さ…
-

連載10273回 健康というストレス <4>
(昨日のつづき) 人間とは、食べる動物である。私たちは食べなければ生きていけない。もちろん人工栄養で生命を維持する例もあるが、それでは本当の意味で生きていることにはならないだろう。 何を、どう…
-

連載10272回 健康というストレス <3>
(昨日のつづき) 小学館から出ている健康関連本のなかに<片寄斗史子聞き書きシリーズ>という一連の出版物がある。 片寄さんは私が信頼するベテラン編集者で、このシリーズも良心的な健康本として愛読し…
-

連載10271回 健康というストレス <2>
(昨日のつづき) 60歳を過ぎた頃から、小便の勢いがなくなってきた。トイレの朝顔を前にシャーッと盛大に放尿する快感が失われてきたのだ。 今ではマナー違反だろうが、私の若い頃には、立ちションは青…
-

連載10270回 健康というストレス <1>
<健康という病い>。それを私は<健康病>とよぶ。もちろんそういう病名はない。 しかし、このところこの国に蔓延しているのは、前代未聞のこの病気ではないかと思う。私の場合、目を覚ますとまず頭をよぎるの…
-

連載10269回 根なし草排除の感情 <4>
(昨日のつづき) 少数者である弱者を、弱者の少し上のグループが迫害し、差別する。これは古くからくり返されてきた構図です。 余裕のある階層は、それを黙って見ているだけです。ときには背後からその相…
-

連載10268回 根なし草排除の感情 <3>
(昨日のつづき) 多数者の集団が少数者の集団を憎悪し、圧迫する。この感情は人間の根元的な根づよい感情です。いくら口で智恵と慈悲の教えとか、自利利他とかとなえていても、内部にうずまくどろどろした感情…
-

連載10267回 根なし草排除の感情 <2>
(昨日のつづき) 少数民族を含むミャンマー国民と、非・国民として排除されようとしているロヒンジャの人びとの間には、どのような越えがたい溝があるのか。 ミャンマー国民は、そのほとんどが仏教徒だと…
-

連載10266回 根なし草排除の感情 <1>
このところミャンマーの国家指導者、アウンサンスーチーの言動が国際社会の注目を集めています。 アウンサンスーチーといえば、1991年のノーベル平和賞の受賞者です。たびかさなる政治的迫害にもめげず、…
-

連載10265回 健康は命より大事か <5>
(昨日のつづき) 私がいま感じているのは、この国の人びとが異常なほど健康について神経質になっているのではないかということだ。 それは自分自身にもいえることである。何か食事をする際に、ふとこれは…
-

連載10264回 健康は命より大事か <4>
(昨日のつづき) 健康、ということについても、私は私なりに気を配ってきたつもりである。たとえば、少しぐらい体調が悪くてもすぐに薬を飲まない。病院に行かない。じっと寝て、死んだふりをしている。あまり…
-

連載10263回 健康は命より大事か <3>
(昨日のつづき) 私は戦後70年あまり、今年の春まで一度も病院というものに行ったことがなかった。健康保険は払うもの、それを使わないのが自分流のボランティアだと考えていたのだ。 とはいうものの、…
-

連載10262回 健康は命より大事か <2>
(昨日のつづき) 長寿が、文句なしに目出たいことのように思われていた時代があった。90歳、100歳ともなれば新聞に取りあげられたり、自治体から表彰されたりしたものである。 しかし、今はそうでは…
-

連載10261回 健康は命より大事か <1>
<健康>という名の病いが日本列島に蔓延している。 新聞・雑誌を開けば健康特集、テレビをつければ健康番組、まさに健康問題の大流行だ。 薬品や医療に関する告発記事も多い。生活習慣病という言葉も広く…