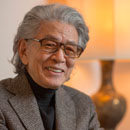五木寛之 流されゆく日々
-

連載11277回 高齢者大国の現実 <4>
(昨日のつづき) 考古学者の網干善教さんは、インドで祇園精舎の発掘調査をやった碩学である。私は『風の王国』という大和を舞台にした小説を書くときに、いろいろ教えていただいたことがきっかけで、その後も…
-

連載11276回 高齢者大国の現実 <3>
(昨日のつづき) 科学的、理論的に物事を考えよ、とは常に言われる言葉だ。 その反対が直感的、情緒的な推論だろう。しかし私は少年時代から数字が苦手で、物事を論理的に思考することが得手でなかった。…
-

連載11275回 高齢者大国の現実 <2>
(昨日のつづき) 前にも書いたが、アフリカのナイジェリアといっても、すぐにはイメージがわかない。 しかし人口2億ちかくときけば驚く。正式名称がナイジェリア連邦共和国。 2020年の調査で、…
-

連載11274回 高齢者大国の現実 <1>
数年前から左脚が痛むようになってきた。歩き回るのが商売の私としては、手と同じように大事な脚である。 戦後70年の私の生活は、2本の脚にかかっていたと言ってもいいだろう。 38度線をこえて、北…
-

連載11273回 「面白半分」こぼれ話 <5>
(昨日のつづき) 新型コロナの蔓延とともに「不要不急」という言葉が、しきりと用いられるようになった。 ふり返ってみると『面白半分』などという雑誌は「不要不急」そのもののマガジンではあった。 …
-

連載11272回 「面白半分」こぼれ話 <4>
(昨日のつづき) 10月13日付けの西日本新聞文化面では、かなり大きなスペースをさいて八女市の『面白半分展』の企画が紹介されていた。 田崎廣助美術館の展示会場では、『面白半分』の雑誌を古書店で…
-

連載11271回 「面白半分」こぼれ話 <3>
(昨日のつづき) 『面白半分』で記憶に残っているのは、いわゆる「四畳半襖の下張裁判」の事件である。 野坂昭如編集長のときに、紙面に掲載された金阜山人の『四畳半襖の下張』が猥褻だとされて、編集者・…
-

連載11270回 「面白半分」こぼれ話 <2>
(昨日のつづき) 本のオビ、通称「腰巻き」は、ふつう5、6センチ幅のベルト状の紙面に短いコピーを印刷したものである。キャッチというか、刺戟的なコピーや、有名人の推薦文や、著者の顔写真などを印刷して…
-

連載11269回 「面白半分」こぼれ話 <1>
先月、10月13日付けの西日本新聞文化面に『面白半分』についてのユニークな記事がのっていた。山下武雄記者の署名記事である。 私の郷里である福岡の八女市にある田崎廣助美術館の片隅で、雑誌『面白半分…
-

連載11268回 小泉文夫さんとの対話 <4>
(昨日のつづき) 小泉さんは優れた旅行家でもあった。アジア各地はもちろん、シルクロードの果てまで音楽の起源をめぐる旅を敢行している。 <「この夏は、まず蒙古へ行きまして」> と、小泉さんは語…
-

連載11267回 小泉文夫さんとの対話 <3>
(昨日のつづき) 今でも思い出す事がある、と小泉さんは愉快そうに話しだした。 芸大の授業に、三波春夫を招いて講義をさせた話である。芸大では日本語の発声法というものをちゃんと教えない。イタリア語…
-

連載11266回 小泉文夫さんとの対話 <2>
(前回のつづき) 私はしゃべることを表現の基本と考えているので、「対談集」を出すときには、かなりエネルギーをかけて作ってきたつもりである。 昭和期に編集した「対談集」の中で、いまも記憶に残って…
-

連載11265回 小泉文夫さんとの対話 <1>
一般に文庫には巻末に「解説」というものがついている。 書店で新しい文庫を手にとると、まずページをめくって「解説」を読むというのがおおかたの読者の習慣だろう。 一般に「解説」は、その作品の付録…
-

連載11264回 内田和博のクオリア <5>
(昨日のつづき) この『よみがえるロシア』は、私の記憶に残る対談集だった。 モスクワ郊外のブラート・オクジャワの別荘に彼を訪ねて、かなり長時間の対話を試みたのだ。オクジャワは雪どけ前のソ連で、…
-

連載11263回 内田和博のクオリア <4>
(昨日のつづき) 内田クンの編纂した著作目録から、対談・座談本を数えてみた。前述の通り私の第1冊目の対談本は『白夜の季節の思想と行動』である。開高健とか、そんな人たちとの討論をまとめたものだ。 …
-

連載11262回 内田和博のクオリア <3>
(昨日のつづき) 内田和博編の単行本・文庫の刊行年譜を眺めて、あらためて思ったのは対談集が意外に少ないことである。 私は以前から書くことと喋ることを同じレベルで考えてきた人間だ。 ブッダを…
-

連載11261回 内田和博のクオリア <2>
(昨日のつづき) 2人の「ウチダくん」のもう片方が、内田和博氏である。彼が私の前にあらわれたのは、もう数十年も前のことだ。当時は彼のことは何も知らなかった。ただ私の書くものを初期の頃からほとんど読…
-

連載11260回 内田和博のクオリア <1>
<細く、長く>というのが、私のひそかな信条である。いや、信条などというご立派な傾向ではない。生れながらの性癖といったほうがいいだろう。 なにごとも熱っぽいのが苦手である。 自動車レースでいうな…
-

連載11259回 49年目の泉鏡花賞 <5>
(昨日のつづき) これまで鏡花賞が歩んできた道を、あれこれ回顧している折りに、突然、瀬戸内寂聴さんの訃報が届いた。 おん年99歳とあれば、希なる長寿である。しかし、気持ちとしては意外に思われる…
-

連載11258回 49年目の泉鏡花賞 <4>
(昨日のつづき) 第1回目の選考委員の中に、森山啓さんの名前を見て、これは誰だろうと首をかしげる若い人もいるかもしれない。 森山さんは、私がたって委員就任をお願いした地元在住の作家のお一人であ…