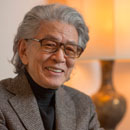五木寛之 流されゆく日々
-

連載10340回 『東京タワー』を歌う <3>
(昨日のつづき) 人間を他の生物と区別するものは、「言葉」であるという。犬や猫にも言葉はあるにちがいないが、やはり言語の発生は、人類の歴史とともにあると言っていいだろう。 しかし、私は「言葉」…
-

連載10339回 『東京タワー』を歌う <2>
(昨日のつづき) 私が九州の田舎から上京したのは、昭和27年(1952年)のことだった。博多駅から24時間かけて列車で東京に着いたのだ。 『鉄腕アトム』が登場したその年は、またマーシャル諸島で水…
-

連載10338回 「東京タワー」を歌う <1>
ひさしぶりに歌謡曲のレコードを出した。コロムビア・レコードから先週発売された『東京タワー』という歌である。あまりにもベタな曲名と思われるかもしれない。しかし、昭和歌謡へのエレジーと考えれば、照れる必…
-

連載10337回 今週読んだ本から <5>
(昨日のつづき) 今週ではなく、先々週に読んだ本を何冊かあげておく。坪田譲治文学賞の候補作品として主催者から送られてきた4冊の単行本だ。 坪田譲治といえば児童文学者として知られているが、その作…
-

連載10336回 今週読んだ本から <4>
(昨日のつづき) 相変らず睡眠時間がアナーキーになってしまって、もとにもどらない。 午前5時か6時にベッドにはいるのだが、2、3時間眠ると、必ず目が覚めてしまうのだ。 ぬる目の風呂に入って…
-

連載10335回 今週読んだ本から <3>
(昨日のつづき) 気象庁の予測が今回は見事、適中して、東京はひさしぶりの雪である。 そういう折りも折り、大阪へ講演で出かける事になった。タクシーはまったくつかまらず。駅のキオスクの弁当コーナー…
-

連載10334回 今週読んだ本から <2>
(昨日のつづき) 鎌田東二さんの『言霊の思想』(青土社刊)を、ようやく読み終えた。なんといっても441ページもある大著である。鎌田さんは年を重ねるごとにエネルギッシュになっていくようだ。百歳を迎え…
-

連載10333回 今週読んだ本から <1>
テレビをつけると、お笑い番組ばかりなので、最近はほとんどテレビを見なくなった。 笑うことにあきあきしているわけではない。いかにも手なれた笑わせぶりが目について、つい鼻白んでしまうのである。 …
-

連載10332回 夜と昼のあいだに <5>
(昨日のつづき) 最近、ヘルス・リテラシーという言葉をよく耳にするようになった。 要するに氾濫する様々な健康情報の中から、正しい知識を選択する能力、ということだろうか。 高齢に達しても働け…
-

連載10331回 夜と昼のあいだに <4>
(昨日のつづき) 地下鉄をおりて芝公園のあたりを歩いていたら、スーパーカーや超高級車のショーウィンドゥがあちこちにできていてびっくりした。 フェラーリやロールスロイス、その他の店が東京タワーの…
-

連載10330回 夜と昼のあいだに <3>
(昨日のつづき) 今日は坪田譲治賞の選考会に出席。どうやら直木賞の選考日でもあるらしく、幾人かの編集者に予想をきかれて答えに困惑する。 直木賞の選考委員をやめてから、もうかなりたっているし、最…
-

連載10329回 夜と昼のあいだに <2>
(昨日のつづき) 今夜も眠れないままに枕元に本を積みあげて、朝まで(午後まで)ベッドの中にいる。 星文社の木下邦彦さんからもらった樋口陽一著『個人と国家』(集英社新書0067A)のページをめく…
-

連載10328回 夜と昼のあいだに <1>
今日は午後7時に目覚めた。このところ睡眠のリズムが大幅に狂ってしまって、どうしても元にもどらない。 元といっても午前6時就寝、午後4時起床というのがふだんの生活である。 夜中に原稿を書く暮し…
-

連載10327回 年頭雑感あれこれ <4>
(昨日のつづき) 全国各地、大雪で大変らしい。「長崎は今日も雪だった」などとテレビの司会者が駄洒落を言っていたが、画面を見ていると相当な積雪である。 しかし、東京周辺の関東地区では、まったく雪…
-

連載10326回 年頭雑感あれこれ <3>
(昨日のつづき) 1935年の朝鮮財界の様子を、前述の『大日本・満州帝国の遺産』には、当時の雑誌記事からの引用として、次のように紹介している。 <(前略)「千載一遇の戦争好景気来! どのようにし…
-

連載10325回 年頭雑感あれこれ <2>
(昨日のつづき) 元日からの1週間、ほとんど本や雑誌を濫読して過ごした。 ありがたいことに体力の衰えにもかかわらず、耳と眼だけはなんとか役に立っている。もっとも5、6時間もベッドの中で活字を読…
-

連載10324回 年頭雑感あれこれ <1>
今日は雨。1月に雨は似合わない。東北はかなりの豪雪らしいが、関東では雪に変る気配はない。このところちょっとした地震がくり返しやってくる。なんとなく不穏な新年だ。 書店をのぞくと、昨年の暮に幻冬舎…
-

連載10323回 今年はどうなる? <2>
(昨日のつづき) 世間の様子から現実を簡単に判断することができない。時代の趨勢を具体的な日常から推理することが難しい時代になったのだ。 昔は世の中の景気はタクシーのドライバーにきけ、という話が…
-

連載10322回 今年はどうなる? <1>
いよいよ平成30年。今年はどんな年になるのか? 私自身もぜひ知りたいところだが、一向に見当がつかない。 10年、20年先の予測は、いろいろ話題になっている。いわく、人口の減少。高齢化。少子化…
-

連載10321回 「マサカの時代」は続く <4>
(昨日のつづき) 『流されゆく日々』のこの一年も、今回で終りである。しかし、来年も『流されゆく日々』は続く。いや、続くだろう。誰にも明日のことなどわかりはしないのだ。私が倒れることもあるかもしれない…