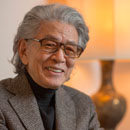五木寛之 流されゆく日々
-

連載11037回 アクセルとブレーキ <2>
(昨日のつづき) 政治家とは政治のプロであるべきだ。 実際にそうであるかないかは別として、そうでなくては困る。 アクセルだけを踏みっぱなしでは運転はできない。といってブレーキを踏んでいるだ…
-

連載11036回 アクセルとブレーキ <1>
12月も半ばである。今年は特別な年だ。新型コロナ感染者の数が、全世界で7000万人をこえた。 死者の数も160万あまりに達している。 なんといってもアメリカは凄い。1600万ちかい感染者と、…
-

連載11035回 「本願ぼこり」と親鸞の呟き <5>
(昨日のつづき) 「本願ぼこり」は、宗門内の言葉で、一般には「造悪説」と呼ばれる。 悪人正機の教えを曲解して、悪をなせばなすほど救いがあるとする立場だ。当然、それは正統的な真宗の立場からは厳しく…
-

連載11034回 「本願ぼこり」と親鸞の呟き <4>
(昨日のつづき) 「本願ぼこり」という耳なれない言葉について書くのは、仏教用語の解説のまねではない。かつて戦後の一時期、イデオロギーが「本願」であった時代があった。 「本願ぼこり」は「イデオロギー…
-

連載11033回 「本願ぼこり」と親鸞の呟き <3>
(昨日のつづき) また12月8日がやってきた。 12月8日。 それは私たち戦争の時代に育った世代にとっては、忘れることのできない特別な日だ。 昭和16年12月8日。 「昭和」で言って…
-

連載11032回 「本願ぼこり」と親鸞の呟き <2>
(昨日のつづき) 宗門では「本願ぼこり」と称するが、これは、「本願誇り」のことだろう。 それまで官製仏教の枠外におかれて、生きて地獄、死んで地獄、と絶望しきっていた底辺の人びとがいた。 い…
-

連載11031回 「本願ぼこり」と親鸞の呟き <1>
「本願ぼこり」という言葉がある。 法然、親鸞の時代に、「悪人正機」という思想が人びとを驚かせた。 救いを求め、わが名を呼んで帰依する者すべてを助けるという驚天動地の教えである。世にいう悪人、非…
-

連載11030回 古い背広で心も軽く <5>
(昨日のつづき) 最近の新聞を見てみると、昭和期の流行歌、いわゆる懐メロのシリーズの広告が目立つ。 一ページでどーんと大きな全集の広告が出るのは、それなりに需要があるからだろう。 テレビで…
-

連載11029回 古い背広で心も軽く <4>
(昨日のつづき) 外出するときに、ついマスクをするのを忘れて慌てることがある。 慎重な人ならバッグに予備のマスクを用意していたりするのだろうか。取りにもどるのも面倒だし、近くのコンビニに駆けこ…
-

連載11028回 古い背広で心も軽く <3>
(昨日のつづき) 本は厄介だ。読み終えたあと、どこへどう保存しておけばいいのか見当がつかない。書庫に並べておけばいいじゃないかという人がいるが、当節の住宅事情をご存知ないのだろう。 そもそも私…
-

連載11027回 古い背広で心も軽く <2>
(昨日のつづき) きょう久しぶりに若い編集者と会った。 この年になると、打ち合わせをする相手も結構、年配のベテラン編集者が多い。昔の話がツーカーで通じるから、お互いに楽なのだ。 「川上宗薫さ…
-

連載11026回 古い背広で心も軽く <1>
最近、コロナのせいで外出を控えているせいもあるが、さっぱり物を買わなくなった。 靴や、カバンや、服のたぐいも、この10年ほどほとんど購入していない。年齢のせいで流行に気を使わなくなったせいもある…
-

連載11025回 ベートーベンも泣いている <4>
(昨日のつづき) ニューヨークの株価、初の3万ドル。 東証も高値更新で2万6000円越えだと。 世の中が大変なときに、一部の富裕層だけが黙っていても肥え太るのが末期資本主義というものだ。若…
-

連載11024回 ベートーベンも泣いている <3>
(昨日のつづき) 先日、『正常性バイアス』という聞き慣れない言葉のことを書いた。 その舌の根も乾かないうちに、いや、これは譬えがちがうか。耳の垢も乾かないうちに、またまた新しい言葉が登場してき…
-

連載11023回 ベートーベンも泣いている <2>
(昨日のつづき) きょうの新聞朝刊の記事。 毎日新聞と社会調査研究センターが共同で先日おこなった全国世論調査では、菅内閣支持率は若い世代ほど高く、高齢者層ほど少い。 日本学術会議の任命拒否…
-

連載11022回 ベートーベンも泣いている <1>
ちかごろ毎日のように見慣れぬ横文字の新語が新聞・雑誌に登場してくる。 最近よく目にするのが<正常性バイアス>という言葉だ。 <バイアス>のほうは、なんとなくわかる。 モノを片寄った場所から…
-

連載11021回 日刊ゲンダイ創刊のころ <10>
(昨日のつづき) 当時の『流されゆく日々』の文章を、ここで一つピックアップしてみることにしよう。 1976年8月26日号に掲載されたものである。 <『話の特集』の編集長が、アリと会いませんか…
-

連載11020回 日刊ゲンダイ創刊のころ <9>
(昨日のつづき) 1975年、創刊当時の『日刊ゲンダイ』の<流されゆく日々>には、どんな原稿を書いていたのか。 ほとんど忘れてしまっている。有難いことにタイトルの総目録が残っているので、それを…
-

連載11019回 日刊ゲンダイ創刊のころ <8>
(昨日のつづき) 文章が前後して申訳ないが、とりあえず1975年(昭和50年)、日刊ゲンダイ創刊の頃の話の続きとご了解いただきたい。 当時から現在まで、この欄を担当してくれているのがI君である…
-

連載11018回 日刊ゲンダイ創刊のころ <7>
(昨日のつづき) 『日刊ゲンダイ』誌、創刊の頃の話にもどる。 当時の原稿のタイトルを拾って羅列してみよう。 <『阿佐田哲也杯』が巷に続出すること>(’75年10月30日・NO3) <金沢芸者…