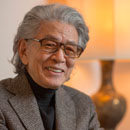五木寛之 流されゆく日々
-

連載12296回 日々是好日ではない <3>
(昨日のつづき) 日刊ゲンダイ紙は、このところかなり高レベルの健康に関する記事が目立つ。 いろんな雑誌が大見出しで喧伝しているような通俗的健康特集ではなく、実質的に体験を通じての記事が多いので…
-

連載12295回 日々是好日ではない <2>
(昨日のつづき) ベッドから起きあがって服を着るとき、ふと足の指を見てびっくりした。足指の爪、ことに親指の爪が異様に伸びているのである。 体全体は老化しているのに、どうして足の爪のような部分が…
-

連載12294回 日々是好日ではない <1>
私が癌になり、それを「公表」した、という新聞記事が原因で、いまだに見舞いの連絡が続いている。 先日、テレビ朝日の<羽鳥慎一モーニングショー>にちょっと出たので、それを見て安心した人も多いらしい。…
-

連載12293回 大河の流れに逆らって <5>
(昨日のつづき) 今回の『大河の一滴最終章』のなかで私が書いたのは、「運命に逆らう」ということだった。 しかし、それは逆流して河をさかのぼることではない。よどみ、渦巻く水流を迂回することであっ…
-

連載12292回 大河の流れに逆らって <4>
(昨日のつづき) ここで、ちょっとドラフトする。文章が横すべりするのも、私の書くものの本質なのだ。 一つのことを正面からだけ語るのでは、語り手のほうも退屈する。ここは遊び心を駆使して、ちょっと…
-

連載12291回 大河の流れに逆らって <3>
(昨日のつづき) 私が『大河の一滴』という本を出したのは、30年ほど前の話である。「生きる」ということ、「死ぬ」ということ、などについて、大人の童話といった感じの物語りを綴ったものだった。今も文庫…
-

連載12290回 大河の流れに逆らって <2>
(昨日のつづき) 今では癌はさしてめずらしい病気ではない。私の担当の編集者の中にも、以前、癌を発症して回復、以前と同じように仕事をしている人が何人かいる。 また、サッカー界のレジェンド、故・釜…
-

連載12289回 大河の流れに逆らって <1>
この数日間、いろんなかたから見舞いのお電話を頂いて、恐縮しているところだ。 どうやら私が癌になったことを「公表した」というニュースが新聞に出たらしい。 たぶん数日前に発売になった『大河の一滴…
-

連載12288回 活字世代の回想など <4>
(昨日のつづき) セメント倉庫の集団生活のなかで、発疹チフスが流行した。体に赤い発疹があらわれ、高熱を発してコロッと死ぬ。 シラミが媒介するといわれた。延吉方面から逃れてきた満州からの避難民が…
-

連載12287回 活字世代の回想など <3>
(昨日のつづき) 子供の頃、スポーツといえば冬のスケートだった。ソウルにいた頃は漢江、ピョンヤンでは大同江が冬の天国である。 大きな河で、氷結すると荷馬車でもトラックでも通ることができる。 …
-

連載12286回 活字世代の回想など <2>
(昨日のつづき) 選挙の結果は、ほぼマスコミの予想どおりとなった。テレビ各局の報道も、どことなく冷静である。意外性というものを、最初から想定していなかったゆえのクールさだろう。 選挙といえば、…
-

連載12285回 活字世代の回想など <1>
午後に目覚めてカーテンをあけると、雪が残っていた。ふと、二・二六事件のことが頭に浮かんだ。 桜田門外の変も雪の日、赤穂浪士の討入りも雪。雪にはなにか不穏なイメージがつきまとう。 昔、『新雪』…
-

連載12284回 古い記憶の断片から <10>
(昨日のつづき) 若い頃、と、いっても40代の半ばぐらいだっただろうか。ロスアンジェルスでヘンリー・ミラーの家にしばらく滞在したことがある。ホキ徳田が紹介してくれたのだ。 ヘンリーさんは卓球が…
-

連載12283回 古い記憶の断片から <9>
(昨日のつづき) もう60年以上も昔のことになる。 敗戦から20年ほど、一般の日本人は外国に出ることができなかった。普通の日本人が海外へ渡航することができるようになったのは、1960年代半ばの…
-

連載12282回 古い記憶の断片から <8>
(昨日のつづき) 平壌から必死で脱北して北緯38度線をこえ、米軍キャンプにたどりついた私たち一家は、しばらくそこにとどめおかれた。なんでも韓国で鉄道のストライキがおこって列車が動かないという話だっ…
-

連載12281回 古い記憶の断片から <7>
(昨日のつづき) 民俗学者の宮本常一さんがどこかで、こんなことを書いていたのが断片的な記憶として残っている。 <農村を歩くと、村の家々から同じラジオの歌声が流れてくる>というのだ。その歌声は『三…
-

連載12280回 古い記憶の断片から <6>
(前回のつづき) 小学校(のちに国民学校となった)の低学年のころである。 母親と並んで庭に面した縁側で何か話をしていた。 ふと、母親が黙り込むと、しばらくしてぽつんと私にきいた。 「もし…
-

連載12279回 古い記憶の断片から <5>
(昨日のつづき) 記憶というのは不思議なものだ。 深刻な体験が必ずしも強く記憶にきざまれているとは限らない。逆になんでもないちょっとした記憶が、いつまでも消えずに残っていることもある。 自…
-

連載12278回 古い記憶の断片から <4>
(昨日のつづき) 敗戦後、まもなくソ連軍が平壌に進駐してきた。 それまで通用していた朝鮮銀行券にかわって、ソ連軍発行の軍票が流通するようになった。 簡単な紙にブルーがかった色で印刷された軍…
-

連載12277回 古い記憶の断片から <3>
(昨日のつづき) 戦時中の小学生が熱中した遊びの一つに、模型飛行機づくりがあった。 紙と木、それに竹ヒゴなどを使って、実際に飛ぶ飛行機を作るのである。 一本の木を胴体にしてプロペラをつけ、…