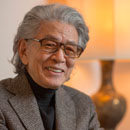五木寛之 流されゆく日々
-

連載12256回 昭和の「モノ書き」たち<1>
いよいよ令和7年も暮れる。 師走の街にはメッチャ車が走り回っている。タクシーも稼ぎどきと見えて、なかなか空車がつかまらない。 物書き稼業も大忙しだ。連載の締め切りも前倒しだし、年頭の感想など…
-

連載12255回 師走に思う人びと <5>
(昨日のつづき) <恩師>という言葉は、手垢がつきすぎていて、使うのが気になるところがある。 それでも、私にとって、あえて<恩師>という言い方をすれば、横田瑞穂先生以外にはいないだろう。仕事の上…
-

連載12254回 師走に思う人びと <4>
(昨日のつづき) かなり前に世を去った作家だが、なぜか歳末になると森敦さんのことを思い出す。 森さんは長い雌伏のすえ、名作『月山』で文壇に再登場したベテラン作家である。 酸いも甘いも噛みわ…
-

連載12253回 師走に思う人びと <3>
(昨日のつづき) 今年、鎌田東二さんが亡くなったときはショックを受けた。踏んでも蹴ってもクタバラないような不死身の人、というイメージがあったからだ。 鎌田さんと知り合ったのが、どんな時期で、ど…
-

連載12252回 師走に思う人びと <2>
(昨日のつづき) 友人、というのは、少くとも30年以上つきあってきた友達のことを言うのではないだろうか。 友人の多いことを自慢する人もいるが、それは一種の社交ではないかと思う。 私の仕事仲…
-

連載12251回 師走に思う人びと <1>
年明け早々に出す新刊の原稿が、まだ、あがっていない。この数日が勝負というわけで、ひさしぶりに徹夜の仕事が続く。 そうでなくても、年末はあわただしい時期である。連載をこなしながら、いろんな原稿を書…
-

連載12250回 再び「歩く」ことについて <6>
(昨日のつづき) 「人間は考える葦である」 と、いう。 「葦」であるから恰好いいのであって、これが「考えるセイタカアワダチソウ」だったりしたら、千古の名言とはならなかっただろう。 とりあえ…
-

連載12249回 再び「歩く」ことについて <5>
(昨日のつづき) むかし中国のいろんな寺を訪れたことがある。社会主義体制下でも、仏教は根強く生きているのだ。 中国の禅発祥の寺といわれる古寺を訪れたときに、不思議な光景を目にした。 寺の門…
-

連載12248回 再び「歩く」ことについて <4>
(前回のつづき) 夜中の地震にすっかり気が動転してしまって、連載を1回とばしてしまった。(つづき)になっている話をつづけよう。 「食事」と「睡眠」と「運動」。 この3つが健康を維持する主要な…
-

連載12247回 揺れる列島、ふたたび
夜、原稿を書いていたら、窓がギシギシ音をたてはじめた。 時間は11時30分すぎ。 すぐにテレビをつける。北海道、東北地方に津波警報が出ている。 マグニチュード7.6あまりのようだ。 …
-

連載12246回 再び「歩く」ことについて <3>
(前回のつづき) 身体のコンディションを整える基の3つは、食事、睡眠、運動であるとは、天下の常識である。 そして、それぞれの部門に関して、百人百様の意見がある。 私も最初のころは、かなり独…
-

連載12245回 再び「歩く」ことについて <2>
(昨日のつづき) 以前『週刊新潮』に、歩くことについての雑文を書いたことがある。 そのとき、読者のかたから丁重なお手紙をいただいた。 私が「親指を意識して歩くこと」を重視している、と書いた…
-

連載12244回 再び「歩く」ことについて <1>
この数年間、ずっと杖をついて歩いてきた。左膝が痛くて、自由に歩けないのである。 戦後、はじめて病院で診てもらった。いろいろ検査をして、 「変型性膝関節炎ですね」 と、いうことになった。 「…
-

連載12243回 再び初冬の金沢へ <11>
(昨日のつづき) 地元の<テレビ金沢>という局とは長いつきあいで、もう何十年も続いている番組もある。短い番組で、<新金沢百景>というやつだ。音録りは東京でやるのだが、時には金沢の局で録音することも…
-

連載12242回 再び初冬の金沢へ <10>
(昨日のつづき) 金沢では花街のことを「くるわ」と言う。これを遊郭と誤解する人も少くないが、クルワは遊郭ではない。笛、三味線、太鼓、舞踊など、それぞれの芸の修業も積んで、一人前の芸妓としてお座敷を…
-

連載12241回 再び初冬の金沢へ <9>
(前回のつづき) 嵐山光三郎さんが亡くなられた。 毎年、欠かさず出席されていた鏡花賞の選考会に、去年、今年と続けて欠席されたので、ずっと気になっていたのである。 嵐山さんとはじめて会ったの…
-

連載12240回 再び初冬の金沢へ <8>
(昨日のつづき) 通称、ズワイ、ずわい蟹は、初冬の金沢ではなくてはならない風物詩である。 以前、金沢の旧名「杉の井」といった料亭から、ズワイを送ってもらったとき、友人に、 「北陸のズワイ蟹を…
-

連載12239回 再び初冬の金沢へ <7>
(昨日のつづき) この冒頭の「昨日のつづき」という文句に、たまらない懐しさをおぼえる読者は何人いらっしゃることだろうか。 おそらく80歳か90歳以上の世代でなければ、この言葉に特別な興趣を感じ…
-

連載12238回 再び初冬の金沢へ <6>
(昨日のつづき) 昔は、といっても私が大学生だった頃の話だが、金沢へいくには上野駅から出発した。 上信越線回りで、途中から新潟のほうへ回り糸魚川を通って金沢へ着く。 夜明けがたに金沢駅に着…
-

連載12237回 再び初冬の金沢へ <5>
(前回のつづき) 以前にも何度か書いたことがあるが、私には、「ふるさと」はない。また、言いかえれば複数の「ふるさと」があるということにもなるだろうか。 生まれた<ふるさと>は九州、福岡の筑後地…