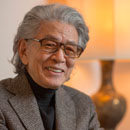五木寛之 流されゆく日々
-

連載12276回 古い記憶の断片から <2>
(昨日のつづき) 昭和20年8月15日に、私たち一家は北朝鮮の平壌で敗戦を迎えた。 父親はそのとき教育召集とかで家にいなかったが、数日後に帰ってきた。 やがてソ連軍が進駐してくると、私たち…
-

連載12275回 古い記憶の断片から <1>
もう10年ほど前のことになる。 ある韓国人の作家と話をしていて戦前、戦中の韓国の話になった。彼は日本本土の生まれで、韓国での生活体験はない。 私は昭和7年の生まれだが、物心ついたときには韓国…
-

連載12274回 戦後の山村の生活 <5>
(昨日のつづき) 私は生後まもなく両親と共に内地を離れた。そして中学1年の時まで外地で暮した。 そして戦後、引揚げてきて本土ですごし今日にいたっている。私が13歳か、その辺の時期を、内地の都市…
-

連載12273回 戦後の山村の生活 <4>
(昨日のつづき) 父の実家にしばらくお世話になったあと、こんどは山ひとつ越えた母の実家に転り込んだ。 飛形山を越えた反対側の山村である。ここも村はずれの山中の小集落だった。 母が帰国前に亡…
-

連載12272回 戦後の山村の生活 <3>
(昨日のつづき) 飛形山の傾面に生い茂っている竹林の中で季節になると筍を掘る。 これはとても素人にはできない。下手をするとタケノコの本体を傷つけてしまうのだ。 地上に出ているのは3分の1か…
-

連載12271回 戦後の山村の生活 <2>
(昨日のつづき) 引揚げ後、両親の実家にお世話になった話は、これまでにも、この欄で何度も書いた。 戦後、農村も大変な時期だったはずだが、私たち家族を受け入れて面倒をみてくれたことには、心から感…
-

連載12270回 戦後の山村の生活 <1>
戦後も八十数年たつと、当時の世相も古い<むかし話>のように聞こえることがある。 私は敗戦後、外地から引揚げてきて、数年間を九州山地の集落で暮らす機会があった。 戦後まもなく母親を失い、子供3…
-

連載12269回 活字文学の末端で <4>
(昨日のつづき) 対談というのは、なんとなく気楽な仕事のように思われそうだが、そうではない。 ワキアイアイといった感じで話が進めばいいのだが、イントロのところでつまずくと取り返しのつかないこと…
-

連載12268回 活字文学の末端で <3>
(昨日のつづき) きょうは今年の「喋り始め」で、『婦人公論』の対談収録。 いわゆる雑誌の「対談」だ。 私が聴き役のインターヴューではないので、ダイヤローグとでもいうのだろうか、わが国のメデ…
-

連載12267回 活字文学の末端で <2>
(昨日のつづき) <活字文学>とは、奇妙なタイトルだが、それは私の個人的予感による表現だ。将来、活字によらない文芸、文学、文化の時代が到来するのではないかという突飛な予感をおぼえる時があるからである…
-

連載12266回 活字文学の末端で <1>
また新たな執筆生活が始った。 「新たな」といっても、昨年の続きである。 昨年の仕事は、その前の年の続き、というわけで、執筆生活は65年目にはいった。 執筆生活であって、執筆ではない。原稿用…
-

連載12265回 新しい年のデジャヴ <5>
(昨日のつづき) この冒頭の文句を<サクジツのつづき>とは、読まないで欲しい、というのが私のひそかな願いである。 <キノウの続き> という往年のラジオ関東の番組へのノスタルジーから引いたセリ…
-

連載12264回 新しい年のデジャヴ <4>
(昨日のつづき) デジャヴ(既視感)をおぼえるような出来事は、この10年の間にもしばしばあった。 しかし、かつて視た現実と重なり合う場面はあっても、やはり昔は昔、今は今である。 似ているか…
-

連載12263回 新しい年のデジャヴ <3>
(昨日のつづき) (déjà vu)というのは、一般に<既視感>と訳される。 前にそれを見たことがないにもかかわらず、以前にもなんだか見たことがあるような気がすることを言うらしい。 以前、『…
-

連載12262回 新しい年のデジャヴ <2>
(昨日のつづき) 職業作家には盆暮れも正月もない。 きょうも夕方、幻冬舎の相馬さんが最終原稿と直しゲラを取りに来訪。午後3時の約束を急遽、6時に延ばしてその間に原稿、あと書きなど10枚あまりを…
-

連載12261回 新しい年のデジャヴ <1>
<月並みは大事>という私のモットーにしたがって、「明けまして、お目出とうございます」と、ご挨拶させていただく。 「なにがどうメデタイんだ?」 などと、頭ごなしに文句をつけたりはしないで頂きたい。…
-

連載12260回 昭和の「モノ書き」たち <5>
(昨日のつづき) サンデー毎日の今週号に、『今年、旅立った人々』という記事がでていた。 外国人をのぞく日本人は15人が挙げられていたが、生前、私が個人的に存じあげていたかたが、6人おらえた。 …
-

連載12259回 昭和の「モノ書き」たち <4>
(昨日のつづき) 今は挿画というが、昭和の頃は<挿し絵>だった。 有名な画家たちも、<サシエ画家>と呼ばれていた。<挿画家>と呼ばれる画家たちの世界にも、大家と駆け出しの新人がいた。 往年…
-

連載12258回 昭和の「モノ書き」たち <3>
(昨日のつづき) 昭和30年から40年代にかけて、中間小説誌の全盛期といっていい時代があった。 老舗の『オール読物』『小説新潮』などを中心に、『小説現代』など新興の小説誌が勢ぞろいして競いあっ…
-

連載12257回 昭和の「モノ書き」たち <2>
(昨日のつづき) 私が新人賞をもらってデビューをはたしたのは、昭和41年である。翌年に直木賞を受けて駆け出しのプロ作家となった。 当時、ノベルス的小説世界で暴れ回っていたのが、<もの書き>出身…