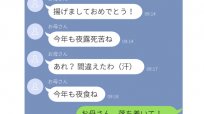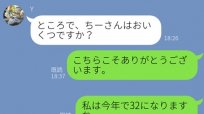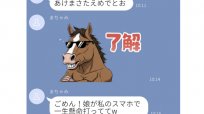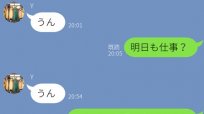年末年始に親と相談したい「改葬・墓じまい」の作法 改葬には「5つの手順」が

コロナ禍で親族すら葬儀を遠慮した例は少なくない。葬儀の在り方や弔い方に対する考えも変わった。先祖代々の墓ではなく、血縁関係のない他人同士が同じ墓に入る「合同墓」、あるいは「散骨」「樹木葬」に注目が集まっている。年末年始は約2年ぶりの帰省になる人もいるだろうが、親族が集まる機会に…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,415文字/全文2,556文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。