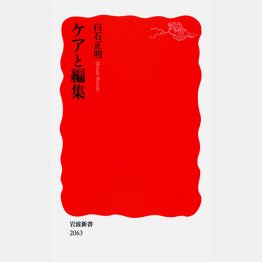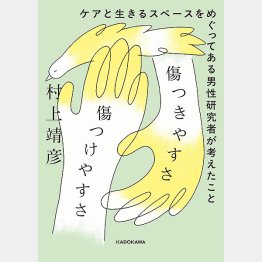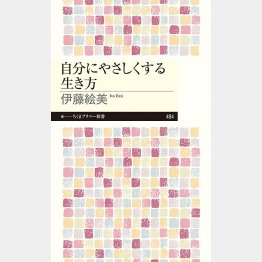ケアの時代
「ケアと編集」白石正明著
ストレスあふれる現代。「ケア」は介護や看護に限らず、現代の困難をやわらげる大事な秘訣だ。
◇
「ケアと編集」白石正明著
医学系専門出版社・医学書院の「ケアをひらく」というシリーズは同社の人気出版物のひとつ。今年3月で計50点を刊行し、うち4点が大佛次郎論壇賞や小林秀雄賞などを受賞。シリーズ全体も6年前に毎日出版文化賞を受けたという。そのシリーズを立ち上げ、43点の編集を担当して定年退職したのが著者。つまり「ケア」という広くて深い世界を書籍というメディアを通して社会に発信・伝達してきた編集者が、「編集」という媒介的な仕事の中で発見したり体験したことを吐露した本というわけだ。
編集者の回想記は世に多数あるが、たいていは著者との間の悲喜こもごものエピソード集。それに対して本書は折々のエピソードをはさみながら、それが「ケア」の世界を自然に読者に伝えることに成功している。巻頭で紹介される北海道にある精神障害者の生活拠点「浦河べてるの家」の話はその好例だろう。「精神病でまちおこし」「昆布も売ります、病気も売ります」と人を食ったキャッチフレーズで知られる同所では年に1回の「べてるまつり」の「幻覚&妄想大会」が大盛り上がりになるという。抱腹絶倒のエピソードの間から、異次元の「ケア」の世界の扉が開く。 (岩波書店 1056円)
「傷つきやすさと傷つけやすさ」村上靖彦著
「傷つきやすさと傷つけやすさ」村上靖彦著
もとはフランス哲学の研究者だったという著者。「若い頃は自己顕示欲が強く、自己主張を激しくしていた」という。
ところがいまは知人と話す場でも口数が少ない。それは医療現場にいる人たちに研究者として聞き取り調査を重ねるうち、相手が看護や子育て支援、あるいはヤングケアラーや被差別の立場にあるにもかかわらず、自分は何一つ当事者としては知らず、「大学教員」という立場で相手を観察しているだけではないかという不安がぬぐえなくなったからだという。つまり「当事者研究」の場にあって自分は非当事者だという負い目だ。しかし著者にも、認知症を患って亡くなった父や祖母との関わりが医療現場への関心のきっかけになったという過去がある。
哲学者が語るケアは医療や看護・介護の技術論ではなく、人と人の関係をめぐる思いのこもごも。「僕たちはどうしたら生きやすくなるのか」と著者は終章で問う。人間の本能のひとつは攻撃衝動。それをどう統御するかが発達のカギになる。それが競争や管理を特徴とする社会構造(特に近代)と結びつくと「暗い欲望」に変質する。自分が社会から排除されるのではないかという不安が他者を排除しなければという衝動を誘うのだ。 (KADOKAWA 1650円)
「自分にやさしくする生き方」伊藤絵美著
「自分にやさしくする生き方」伊藤絵美著
近ごろよく聞くのが「自己評価が低い」悩み。要は自分に自信がないということだが、「自己評価」というと自分を評価する基準を他から押し付けられてきたというニュアンスが出てくる。そんな世の中で「自分にやさしく」とうたう本書は、その意味をストレスから「自分を助ける」ことだという。
教えるのは「自分を生きづらくさせる『心の根っこ』」から自分を解放する「スキーマ療法」。自分のなかに小さな子ども(チャイルド)がいると想像し、その子が傷ついていたらやさしくケアしてあげることだ。自分自身を客観的に見て、そこに不調の根本原因があると発見するわけだ。
しかし言うのは簡単でも実行するのは至難の業。本書はその具体的なノウハウ集のスタイルで解説してゆく。
1日1回、自分の心の中の「ヘルシーさん」が「チャイルド」に「大丈夫だよ」と声がけするのもそのひとつ。
読み進むと、この「チャイルド」、相当にわがままで自制の利かない幼児らしいことがわかる。学級委員や悪ガキタイプの子(小学生)ではなく、ひたすら駄々をこねる幼児というあたりが現代風だ。 (筑摩書房 990円)