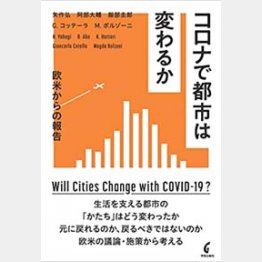コロナ2021
「コロナで都市は変わるか」矢作弘ほか著
ついに年を越し、まだ先行き暗雲のコロナ禍。果たして今年はどうなるのか。
◇
いつ終わるとも知れないコロナ禍の打撃。トランプ政権下のアメリカのような“コロナ後進国”はもとより、スウェーデンや韓国など一時は独自対策でもてはやされた国々もことごとく失敗の烙印を押されつつある。むろん日本の後手後手ぶりはいうまでもないが、悔やんでばかりいても仕方ない。そこで緊急出版されたのが本書。都市社会学や都市計画学などの専門家が日伊から参集して本書を執筆した。
まず問うのは「東京は高密度だから感染が広がった」という説の真偽。たとえば都市を高密度にして移動は車でなく公共交通機関でというコンパクトシティー政策への反対論については、「公共交通がコロナを媒介、拡散させた」とする疫学的な証拠はない。再三危機を伝えられたニューヨークでも密度の高いマンハッタンは実は感染率・感染死亡率とも低かったのだ。
本書では都市はよみがえると考える。コロナは格差のむごい実態をあぶりだしたが、実は金持ちはエッセンシャルワーカーに依存しており、貧者は資本を求める。両者は相互依存関係なのだ。また高密度は「過密」ではないという。問題は密度ではなく「接触」だからだ。そのためには近隣社会の充実と公教育への投資が不可欠。つまりパンデミックはこれまでのゆがみを是正する機会だと説いている。
(学芸出版社 2200円+税)
「コロナ禍の東京を駆ける」稲葉剛、小林美穂子、和田静香編
東京・中野に拠点を置く生活困窮者支援団体「つくろい東京ファンド」。以前から「住まいの貧困」の巣窟だった東京はコロナ禍で一気にホームレス化が進んだ。建築、土木、飲食、性風俗などネットカフェ生活者の仕事の多くがコロナでストップしたからだ。
そこで団体は生活支援と感染リスクの低減の双方に取り組み、「年越し派遣村」型の大規模相談会ではなく、少人数の出動チームが相談者に個別に面会する方式に切り替えたという。そんな活動の記録が本書だが、出版のきっかけはエンタメ系ライターが団体のフェイスブックに掲載された支援者の日記を読んで、コメント欄に「記事にしたい」と書き込んだことだったという。
(岩波書店 1900円+税)
「コロナ後の教育へ」苅谷剛彦著
東大から英オックスフォード大教授に転じた著者は、日本の大学教育についての批判も多数ある。本書でもまずは日本の大学教育批判の筋違いや大学自身の「改革」の勘違いを指摘する。
たとえば日本の大学改革論は、現状はダメだ、こんなにも遅れているという「大学性悪説」から出発する。しかしイギリスでは大学はこれだけの富を生み出している、ゆえにさらなる補助金でより充実させようという「性善説」論法になる。
前者の日本型改革論は実はエビデンス抜きの感情論、改革ありきの改悪になりがちなのだ。コロナ問題についても断定論を避け、100年前のスペイン風邪のときに日本政府や大学がどう対応したのかを丁寧に述べる。
重要なのは未知や不可知の事態をめぐる「無知の知」を恐怖し、その状態に耐えきれずに不安に駆られた人々に対してシャワーを浴びせるように不覚的な情報を浴びせることの危険性を自覚することだという。メディアの自制と自重が重要なのだ。
(中央公論新社 860円+税)