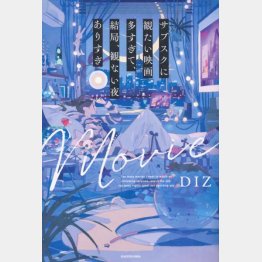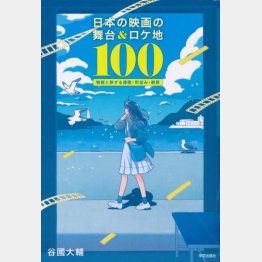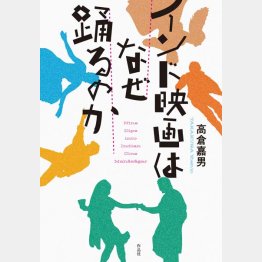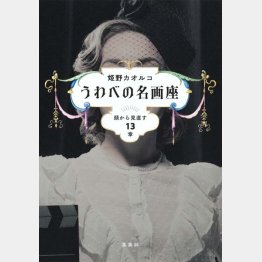“裏”を知って見る楽しみが倍増!映画の本特集
「サブスクに観たい映画多すぎて、結局、観ない夜ありすぎ」DIZ著
我々の目の前に突然、違う世界を見せてくれるのが映画。だが、その背景にはややこしい事情があったり、製作者にとって不本意な評価があったりする。そういう映画を見る楽しみを増幅させてくれる情報が詰まった本を紹介しよう。
◇
「サブスクに観たい映画多すぎて、結局、観ない夜ありすぎ」DIZ著
サブスクは会費のみで「無数の映画を見たいときにいつでも見られる」が、締め切りがないため、見たいものをなかなか決められない。ふだんから見たい映画をマイリストに入れておくことが必要だ。
何かを調べるときはまずグーグル検索をするが、その検索ワードは自分が今、気になるテーマなのだ。それに「映画」をプラスして検索すると、自分が見たい映画に出合える。例えば眠れなくて困っている時は「不眠・映画」で検索すると、不眠に悩む男を描いた「マシニスト」が出てくる。
著者はかつて☆評価を参考にして映画を選んでいたが、それですべてを判断すると、本当に見たい映画と出合えない。結末が明快でスカッとする映画が高評価になりやすく、ホラーなどは低評価になりがちなのだ。
見たい映画に出合うための実践的なアドバイス。 (KADOKAWA 1870円)
「日本の映画の舞台&ロケ地100」谷國大輔著
「日本の映画の舞台&ロケ地100」谷國大輔著
平安時代に実在した安倍晴明の活躍を描いた映画「陰陽師」は、3作品とも岩手県の歴史公園「えさし藤原の郷」で撮影されている。園内には歴史考証に基づいた平安建築群が立ち並ぶ。そのひとつ「伽羅御所」は日本で唯一、平安時代の寝殿造りを再現した建物で、門構えに魔よけの五芒星をつけて晴明邸として撮影に使われた。
1951年にベネチア映画祭で金獅子賞を受賞した「羅生門」で、旅の法師と杣売りが雨宿りしていた羅生門は、大映京都撮影所の敷地内に原寸大で作られたオープンセット。建て込みには約1カ月かかったという。
ほかに、高倉健と松田優作の唯一の共演映画「ブラック・レイン」は、東京では古い建物が少なく、撮影許可も取れなかったので、古い町並みが残る大阪で撮影したなど、意外なエピソードも満載。 (学芸出版社 2200円)
「インド映画はなぜ踊るのか」高倉嘉男著
「インド映画はなぜ踊るのか」高倉嘉男著
1998年に公開された「ムトゥ 踊るマハラジャ」は、インド映画ブームを巻き起こした。副題の「踊るマハラジャ」というフレーズが、日本人の脳裏に「インド映画=踊る」という公式を刻みつけたのだ。この公式のために、日本人がインド映画をほかの国の映画より低く見るような偏見があるのではないかと著者は憂える。踊りが入っている映画は入っていない「標準」の映画に比べて「特殊」だと。
アメリカのミュージカル映画は否定的には扱われないのに、インド映画はそうではない。インド映画では歌と踊りが「突然」「何の脈絡もなく」差し挟まれるからではないか。それは、インドには演劇と舞踊を不可分のものと考える文化があるからなのだ。
ほかにも「なぜ説教臭いのか」など、インド映画の「?」を探る。 (作品社 2970円)
「うわべの名画座」姫野カオルコ著
「うわべの名画座」姫野カオルコ著
最近は「イケメン」と言うが、かつては「ハンサム」と言った。その代名詞だったのがアラン・ドロンだ。
ドロンの顔は甘いが陰がある。ニーノ・ロータ作「太陽がいっぱい」のメロディーを形にしたような顔だ。ナタリー・ドロンと結婚して渡米したのにハリウッドで成功できなかったのは、監督が明るく撮りたかったのにその陰が邪魔したせいだ。だが、若さを失うと人気が凋落する俳優もいるのに、ドロンはその陰のおかげで若くなくなってもノワール映画で活躍できた。「育ちが悪い感じ」などという人もいるが、「太陽がいっぱい」の、貧しい家に育ったトム・リプリーの役はあの陰があってこそ、なのだ。
(「アラン・ドロンと〈ハンサム〉の時代」)
ほかに、「伊豆の踊子」の内藤洋子や山口百恵など、さまざまな「顔」から映画を語る。 (集英社 2090円)