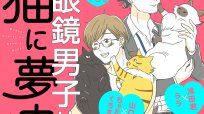お金はあるのになぜ? 増える「老人の万引」をどう減らす

高齢者による万引が後を絶たず、東京都が有識者研究会を立ち上げた。なにしろ2015年に都内で摘発された万引犯のうち、65歳以上が3割近くを占めたのだ。5年前は2割そこそこだったので、存在感はグンと増してしまったことになる。
そういわれても多くのサラリーマンは「うちの親に限…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り836文字/全文977文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。