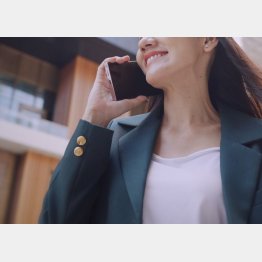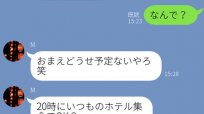「この初老の女が私?」映像に映った“残酷な姿”に凍り付く。もう若くない…悟った女が辿りついた答え【渋谷の女・谷 綾女 45歳#3】
【渋谷の女・谷 綾女 45歳#3】
【何者でもない、惑う女たちー小説ー】
中堅出版社に勤める綾女は、管理職につくことを打診されて落ち込む。失意のうち向かった先は渋谷にある元恋人・崇が経営するバーだった。20年ぶりの再会であったが、現在、共にパートナーのいないふたりは意気投合して……。【前回はこちら】【初回はこちら】
【関連記事】「世帯年収1500万じゃ恥ずかしい」御茶ノ水からの“都落ち”…武蔵小杉のタワマンを選んだ女のプライド【武蔵小杉の女・鈴木綾乃 35歳】
乙女みたいな葛藤、私にできるんだ
開場15分前。まばらに人が集まっている。
朝方、自宅のおふとんでぐっすり眠って、ちょっとだけ日常に戻ったあと、私は再び渋谷へ繰り出した。
昨日来たばかりなのに、少しだけ景色が違って見えるのは気のせいだろうか。
ロフト9の入り口前でスマホを眺め、気怠い大人の女を意識しながら待つ。本当は目を輝かせて待っていたいのになぜか装う。
――こんな、乙女みたいな葛藤が私にできるんだ。
口元のゆるみを必死で抑えた。髪をかき上げ、スマホで時間を見ると、肩にぬくもりを感じた。
満面の笑みで、私は振り向く。欲しい笑顔がそこにあった。
「待った?」
「15分くらい」
「ははっ。待たせてごめんね」
さも当たり前のようにチケットを受け取り、受付を済ませた後は、空いていた最前列に座った。最前といえど、トーク&ライブBARなので、落ちついてドリンクを傾けながら空間を楽しむことができる場所だ。
生ハムと赤ワインをデキャンタで頼み、さっそく乾杯。昨日のお酒のかけらも残っている。まだまだ身体は熱いままだった。
ライブの期待感よりも、彼といる高揚感が私を支配している。ライブの後はどこへ行こうかなんてことを、さっきからずっと考えている。
気が付いたら、手を握り、身体を委ねていた。崇の鼻が私の頬をこする。私もお返しに、頬ずりをする。彼のことでいっぱいで、人の目なんて気にする余裕はなかった。
仕事から解放される自分が心地いい
――昨日は、仕事のことで頭が一杯だったのにな。
いつもと違う自分が心地よかった。私は、まだ、間違いなく28歳だった。
「好きだよ」
崇の声が耳元を撫でる。うん、うん、と頷くと、彼は私に覆いかぶさるように背中からぎゅうと抱きしめた。
照明が一瞬暗くなる。その隙にキスをして、お互いの存在を触覚で確認していると、ステージにSweetSetのふたりがやってきた。
「こんばんは。まずはこの曲からお楽しみください」
アコースティックギターとキーボードだけの簡素なステージ。
ベレー帽に花柄ワンピース。モッズスーツにストライプのネクタイ。あの頃と同じ衣装なのにどこかちぐはぐな違和感をおぼえながらも、それでも歌声は昔のままだった。
当時、CMソングに使用された懐かしの曲に思わず身体を揺らす。すると、演奏する彼らの背景に、観客の様子が映像として映し出された
初老のカップル…え、これが私たち?
あたかも、SweetSetのふたりが大勢の観客に囲まれて歌っているような光景だった。代々木公園のストリートライブ出身の彼ららしい演出である。
身体を揺らし、コロナの瓶を掲げ、懐かしい音楽に浮遊している人々。私も崇も、SweetSetの音楽の一部になって溶けている感覚だった。
――ふふっ。このカップル、なんか…どうなんだろ。
最前列に人目もはばからずいちゃつく初老の男女がいた。まだまだ若い気分ではしゃいでいる姿が微笑ましかった。あんなふうになりたいと思った。その一方で、どこか彼らに冷笑的視点を持っている自分もいた。
「お、俺たち、映ってる」
彼のささやきで、客観が自分に戻った。
「え?」
初老の男女。その正体が私たちだと気づいた時、サッと背中に冷たいものが走った。
「…あれが、私?」
枯れた花。重力に従った男女。薄暗い照明が、重ねた人生のしるしをさらに浮き彫りにしていた。
固まる。周りに目をやる。周囲も同様だった。疲れた目元、くたびれたスーツ姿、体型隠しワンピースで身を包み、全てが落ちついたいでたちの元・若者たち。歌う主役もそう。彼らに感じていた違和感の正体は、それだった。
脳内の自分と現実のギャップに衝撃
気持ちと現実のギャップ。
脳内で描く理想の自分の齟齬。まさに、目の前で突きつけられた気がした。
崇は気にしていないようだった。それでもいい。それが前向きな受け止め方。だけど私は、玉手箱を開けてしまったような感覚に陥った。
私は崇から身体を離す。彼は人目をはばからずノリノリだ。だけど、ライブも中盤に差し掛かった頃、途端に大人しくなった。息が荒くなっていた。
柱代わりに彼に身を寄せる。彼は私にキスをしたそうだったけど、恥ずかしいフリをして顔を逸らした。
汗と、年齢を重ねた男性の匂いを私はかみしめた。
――……いつまでもアラサー気分のままでいいの?……
一番楽しくて、夢中だったあのころに、自分は逃げようとしている。
いや、今までもそうだった。ずっと、輝いていた頃にしがみついて生きていた。これから先も、「あの頃はよかった」そんなことを言い続けながら、私は後ろ向きで歩き続けるのだろうか。
結局、崇は年を取った以外はなにも変わっていなかった。他人としては安心できる存在だけど、きっとまた同じことを繰り返す。後ろ向きのままで。
「この後、どこ行く?」
「疲れたから、帰るね」
「そうだね。2日連続は疲れるよね」
まるで何もなかったかのように、坂の途中で、私たちは次の約束をせずに別れた。
誘いがあれば、会ってもいいけど、少なくとも私は自分から誘う気力はない。それはくたびれた大人になってしまった証拠だ。
置いて行かれたんじゃない。進もうとしなかっただけ
――辞令、うけてみようかな……。
今を思い切り楽しんでいる世代の人波を逆走しながら、もうここは私の街でないことをはっきり理解した。
若者の町に、居心地が悪くなっていたことはわかっていた。
だけど、違うんだと言い聞かせて、必死に抗おうとしていた。時代に、年代に、乗り切れないことを、必死に言い訳して。
駅に向かおうとする足を止めて、タクシーを止める。
タクシー。それがいまの私に相応しい手段。もう若者ではない私は、受け入れるためにあえてそうしてみる。
乗り込むなり、自宅の場所を告げた。
流れてゆく街の景色はいつもの2倍速だ。優越感と町の彩りが目に優しかった。
「お姉さん、ごきげんだね」
運転手のおじさんに声をかけられる。知らぬ間に鼻歌をうたっていたみたいだ。オザケンのアルバム曲、どうやら同世代だそうだ。曲名を簡単に言い当てられた。こころなしか、会話がはずんだ。運転手さんは今、子どもの影響で、アイドルソングにハマっているらしい。
時代に置いて行かれたわけじゃない。進もうとしなかっただけ。まだまだ時代は続いていくのだから、今からでも乗り遅れずに歩むこともできるはず。
坂道を登りきると、そこにはどんな景色が広がっているだろう。
なぜだろう、心なしかワクワクが芽生えている自分に気づいた。
Fin
(ミドリマチ/作家・ライター)