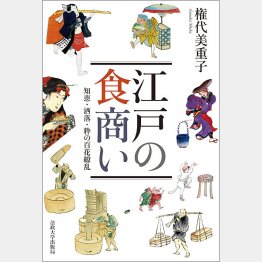「江戸の食商い」権代美重子著
「江戸の食商い」権代美重子著
近頃の日本のテレビは食べ物に関する番組がすこぶる多い。制作費が安いとかさまざまな要因があるだろうが、視聴者の関心が強いということは間違いない。
こうした傾向は今に限ったことではない。昭和のバブル期にも各種のグルメ番組が盛んだったし、さらに遡れば日本人の食べ物への偏愛は江戸時代に始まることが本書を読むとよくわかる。
日本人にとって「食」を空腹を満たすだけのものから楽しむものへと変化させたのは、1日3食の食習慣になったこと、白い米飯が主食になったこと、野菜や魚の集荷流通システムが整ったこと、醤油や砂糖といった調味料の普及の4つで、いずれも江戸時代に始まった。
また100万都市、江戸の住民の7割は長屋や借家住まいで、狭い空間に身を寄せ合うように暮らしていた。画期を成すのは江戸市中の大半が焼失した明暦の大火(1657年)で、復興のため全国から大工・左官・鳶などの職人が集まり、そのほとんどが単身者だった。そのため外食の比率が高まり、各種の「食商い」が隆盛することになる。
1日3食になった元禄の頃から江戸では白米が主食になるが、その後、高価だった醤油と砂糖が安価になったため白米に合う濃厚な味が好まれるようになる。忙しい職人たちにそうした味を提供すべく生まれたのが各種立ち食いの屋台料理で、そこから江戸4大料理と呼ばれる、寿司、天麩羅、蕎麦、鰻のかば焼きが生まれることになる。
商いであるから宣伝や競争も熾烈。水茶屋の看板娘を目当てに大勢の男客が押しかけ、彼女たちをモデルにした芝居や読み物も登場。人気の看板娘を巡ってファン同士が競うなど、まるで現代のアイドルのような騒ぎも。
そのほか、居酒屋や歌舞伎の弁当の誕生、ベストセラーとなった各種料理本、高級料理店に文人墨客が集まるなど、広範な食文化が花開いていく様子が、豊富なカラー図版と共に紹介されていく。 〈狸〉
(法政大学出版局 2750円)