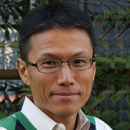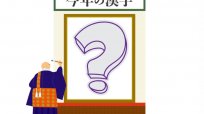鄧小平が残した中国共産党のカタチ 改革開放と天安門事件

グラフをご覧ください。1980年代から中国は高い成長率を続けており、「世界の工場」と呼ばれるようになった様子が分かります。しかし、1989年から90年の一時期だけ、成長率が大きく落ち込んでいます。いったい、なぜでしょうか? 今回は鄧小平(写真①)に焦点を当ててみましょう。
…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,819文字/全文2,960文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。