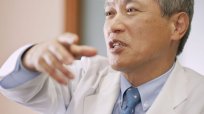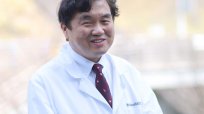(3)生活習慣病に対応したものは? 胃痛や胸やけの薬も登場
スイッチOTC成分は、現時点で96種類。その多くがアレルギー性鼻炎薬、かぜ薬、便秘薬、解熱鎮痛薬、水虫・たむし治療薬などで占められています。もちろんそれらも十分に利用価値はありますが、多くの中高年が気になる生活習慣病(高血圧・高脂血症・糖尿病など)に対応したものは、高脂血症薬が3種類(実質的には1種類)あるだけです。
まず「ソイステロール」。血液中のコレステロール値を下げる効果があります。大豆に含まれる植物ステロール(大豆油不けん化物)のことで、もっとも早い時期(1983年)にスイッチ化されましたが、すでに処方薬としては使われていません。いまは特定保健用食品(トクホ)などの材料のひとつとして、ほそぼそと生き残っているだけです。
「ポリエンホスファチジルコリン」も、血中コレステロールを改善する薬の一種で、1986年にスイッチ化されました。こちらは現役の処方薬としてそこそこ人気があり、いまでも使われ続けています。ところがスイッチOTC薬は、昨年「製造中止」が宣言され、すでに市場から姿を消しています。理由は公表されていません。