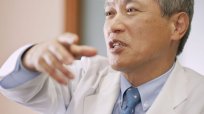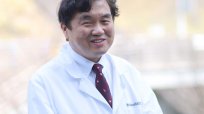体内時計が左右する“食べる時間”の科学…世界が注目の「プレジション栄養学」が描く未来
近年、世界の栄養学で注目を集めている言葉がある。「プレシジョン栄養学(精密栄養学)」だ。性別や年齢だけでなく、遺伝子、腸内細菌、代謝、生活リズムなど、ひとりひとりの生物学的特徴に基づいて最適な食事を設計する考え方だ。
同じ食事をしても体重が増える人と減る人がいる。血糖値の上がり方も人によって異なる。こうした「個人差」を科学的に解明することがプレシジョン栄養学の狙い。解明するための要素はさまざまあるが、早稲田大学名誉教授で愛国学園短期大学特任教授の柴田重信氏は、食べる「時間」に注目した、時間栄養学でプレシジョン栄養に貢献しようと考えている。
「個人差の一因として、『体内時計』の働きに違いがあることが分かってきました。体内時計をつかさどるCLOCKやPERといった遺伝子には個人差(SNPs)があり、それが朝型・夜型の傾向や代謝リズムの違いを生み出しているのです」
柴田氏によれば、こうした時計遺伝子の違いが、食事のタイミングによる栄養利用効率に影響している可能性が高いという。