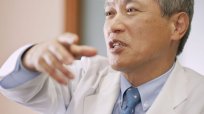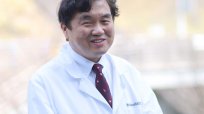生活習慣のさらなる改善が寿命を延ばす…ブルーゾーンで進む長寿環境の探索
寿命を大きく延ばした20世紀。1900年代までの600万年間で20年延長した寿命は、それ以降2000年までの100年間でさらに40年延ばすことに成功した。その大きな原因は、人類が衣食住などでの環境を整えたことにある。
この間、がんやアレルギー、不妊などの病気が劇的に増加したが、それは病気を進化の副作用とするダーウィン医学の立場で見ると、長寿に向けた進化の代償とも言える。
具体例として、前回はがんを取り上げた。花粉症や潰瘍性大腸炎といった「自己免疫疾患」の増加からも説明できる。
本来、人類が保持する免疫能力は自然の中で暮らし、常に外敵に囲まれ体内侵入におびえていた時代に作られた。それに比べて現代は敵が極端に少ない。そのため、免疫組織が力を発揮する敵との邂逅が減った。その結果、ちょっとしたきっかけに過剰に反応してしまうこともあり、これは人類が周りの環境を整備することで長寿を達成した副作用とも考えられる。
では、近年の「不妊」の増加はどうか? 生殖と長寿は負の関係にあり、生殖に費やされるエネルギーにより寿命が犠牲になるといわれてきた。それは無脊椎動物においては線虫やショウジョウバエ、脊椎動物についてはターコイズキリフィッシュなどの生殖細胞除去実験で証明された。生殖細胞除去により、いずれも寿命が延びたのだ。