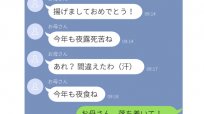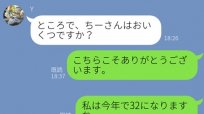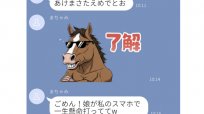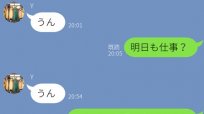無保険や経済的理由での受診控えが招く悲劇…「手遅れ死亡」の恐るべき実態
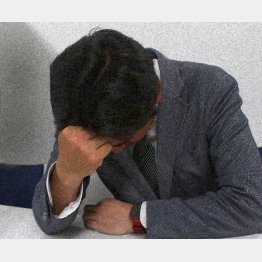
長引くコロナ禍では、院内感染対策から受診を控える動きが拡大。厚労省がまとめた2020年の「病院報告」によると、1日当たりの平均外来患者数は対前年比1割減の119万3205人。統計開始から最大の下げ幅となっている。それで問題なのが、診断時に手の施しようがなく命を落とすケースが珍し…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り3,158文字/全文3,299文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。