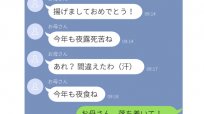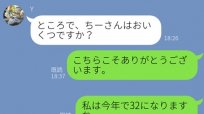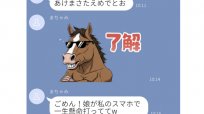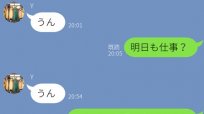昭和37年創業の和菓子店(板橋・大谷口)材料費高騰も子供が小遣いで買える菓子を作り続ける矜持

日大病院の裏手辺りを何げなく歩いていたら、やや唐突に「パステル宮の下」と書いた堂々たるアーチが目に入った。
商店街といえば、大抵駅前から続くもので、有楽町線千川や小竹向原、東武東上線中板橋やときわ台の各駅から10分以上離れた、さらにいえば川越街道にも要町通りにも接しない…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り983文字/全文1,124文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。