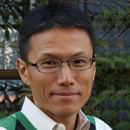西アフリカ国境線の不思議…ギニア湾諸国が“細長い”秘密は「蚊」

地図①をご覧ください。アフリカ大陸西部のギニア湾に面した国々が並んでいます。なんだか不思議な形をしていないでしょうか? 海岸線から内陸部にかけて、国の形が細長くなっていることに気付いたかと思います。これは一体、なぜでしょうか?
■3つの海岸
ギニア湾地域にヨーロッ…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,241文字/全文2,382文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。