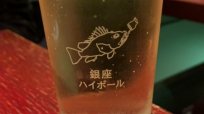「ダニ博士」に聞いた…マダニ感染症もクマ出没も生物と人間社会との距離の問題
五箇公一(国立環境研究所 生物・生態学者)

この夏、マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」が全国で広がり、これまでに感染者は149人と過去最多となった。重症化すると死に至ることもあり、度々ニュースにもなっている。そこで、ダニ研究40年、「ダニ博士」として知られる生物・生態学者を訪ねた。マダニ感染症の増加には、害虫や害獣と人間の距離感という生態系の変化が影響していそうだ。話は最近のクマ出没多発にも及んだ。
◇ ◇ ◇
──「マダニ」と私たちが普段「ダニ」と呼んでいるものは、どう違うのですか。
ダニとひとくくりに言っても、名前がついているだけで5万種以上います。多様性が高く、生息場所も食べる餌もさまざまで、それぞれが全く違う生き物だと考えてください。絨毯や布団など家の中にいるのは「チリダニ」。これは最近、数が増えすぎ、糞や脱皮殻がアレルギーの原因となるため問題になっています。お好み焼き粉や小麦粉の中で大量発生し、アナフィラキシーショックを引き起こした事例も起きています。一方で「マダニ」は動物の血を餌にする。チリダニが1ミリにも満たない大きさに対し、マダニは成長すると4~5ミリあるので肉眼で分かる。普段はシカやイノシシ、クマといった野生動物に寄生していて、当然、人間の血も吸います。その過程で、動物とマダニの間でウイルスがやりとりされ、人間がそうしたマダニにかまれた時にウイルスに感染して病気になる。これがダニ媒介感染症です。
──その中で問題になっているのがSFTSです。なぜ広がっている?
SFTSは、2011年に中国で初めてウイルスが特定された新興感染症です。13年から日本でも患者が出るようになりました。実は、今年発表された論文によると、このウイルスの起源は
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,822文字/全文3,578文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。