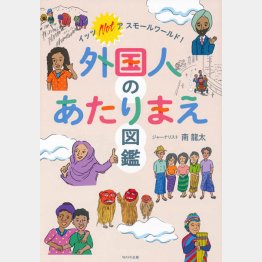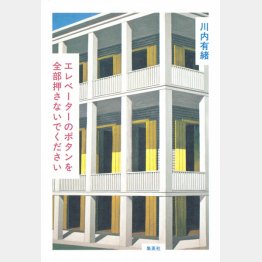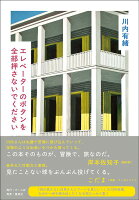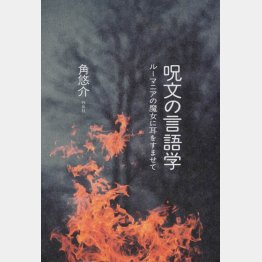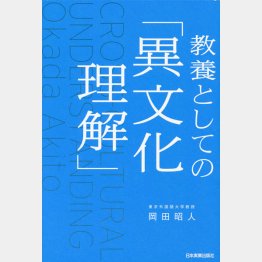今だからこそ読みたい!異文化を考える本特集
「外国人のあたりまえ図鑑」南龍太著
日々、異文化に接しながら暮らしている。コンビニの店員が外国人だったりするのは今や珍しくない。隣室から朗々と響いてくるのは、コーランを唱える声かもしれない。日本とは違う文化と共生するために役立つ本を紹介しよう。
◇ ◇ ◇
「外国人のあたりまえ図鑑」南龍太著
神奈川県北部の人口約4万人の愛川町は住民の約10%が外国人だ。2024年、ブラジル、カンボジアなど外国籍住民による「多言語機能別消防団」が発足した。
消火活動は公道規制などの「公権力の行使」をするので、日本国籍が必要である。そのため、外国人消防団員の活動は避難の呼びかけや避難所での通訳などから始めるなどの工夫をしている。外国籍住民にとって、それは「支えられる側」から「支える側」に変わるきっかけになる。
日本で生まれ育った外国ルーツの2世、3世が増えているが、彼らは親の母国の言葉は話せず、日本語を母語とし、日本人として生きている。それなのに外見だけで「外国人」と見なされ、差別や偏見に苦しんでいるのだ。
外国人を理解するため、世界各国の慣習やタブーなどを紹介した図鑑。
(WAVE出版 2200円)
「エレベーターのボタンを全部押さないでください」川内有緒著
「エレベーターのボタンを全部押さないでください」川内有緒著
著者はノンフィクションライターとしての初めての仕事で、タクラマカン砂漠に行った。かつて楼蘭遺跡を発見した探検家のスヴェン・ヘディンがこの地で命を落としかけたが、著者が訪れた頃には舗装道路が通って車で行ける場所になっていた。
砂漠で車を降りたとき、異様な感覚に襲われる。強い風が吹いているのに何の音もなく、世界は静止していた。高い木や建物といった風を遮るものは何もない。「無」の中で自分だけが「生命体」として存在する。「タクラマカン」とはウイグル語で「死」や「無限」を表す言葉なのだ。そのとき著者は、その言葉がもつ圧倒的な「孤独」を理解した。(「風が吹く場所へ」)
ほかに、パナマのサンブラス諸島で、喉に引っかかった魚の骨をとってくれる「魚の骨取り師」に出会った話など、日常を忘れさせるユニークなエッセー集。
(集英社 1980円)
「呪文の言語学」角悠介著
「呪文の言語学」角悠介著
ヨーロッパといっても西欧と東欧では宗教的に大きな隔たりがある。同じキリスト教国でもルーマニアは「ルーマニア正教」で、西欧で行われた「魔女狩り」は行われなかった。
ルーマニアには現代でも「魔女」がいて、ルーマニアの職業分類には「占星術師」と「数秘術師」がある。だがルーマニアの「魔女」は、日本人が想像するようにとんがり帽子をかぶり、ほうきにまたがって空を飛んだりしない。ルーマニアの「魔術」は民謡や工芸などと同じように人びとに伝えられてきた伝統文化なのだ。伝統文化が根づいている土地では、呪文などの「魔術」は農村生活を豊かにするための人びとの知恵であり、著者は「おばあちゃんのケタ外れの知恵袋」だと捉えている。
ルーマニアに留学し、日本とルーマニアの友好関係の促進をしている著者による言語学エッセー。
(作品社 2640円)
「教養としての『異文化理解』」岡田昭人著
「教養としての『異文化理解』」岡田昭人著
人は無意識のうちに自分が属している文化が「常識」で、それと違うものは「変なもの」と捉えがちだ。中国や中東などで大人の同性同士が手をつないで歩いているのを見ると驚くが、「対人距離」は文化によって異なる。文化の違う国での生活でカルチャーショックを経験したときは、まず情報収集をするとショックを和らげることができる。それだけでなく、自分の感情を適切に表現することも重要だ。ほかの文化を尊重し、理解しようとすることで、誤解や対立を生まないで済む。
法務省の調査では、外国人の知人がいない日本人は41.5%もいる。異文化の人と交流し、友人や知人をつくると、お互いに理解しやすくなる。
ニューヨーク大学などで異文化コミュニケーションを学んだ著者が、さまざまな視点から異文化への対処法をアドバイス。
(日本実業出版社 2200円)