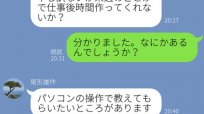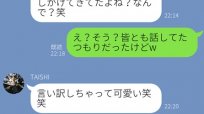「決断」を先送りすると、なぜ不安や心配に苛まれるのか? 脳神経外科医が解説
物事の決断が早い人と遅い人。その違いを脳科学の側面から見てみると?
脳神経外科医の菅原道仁さんが、人をやる気にさせる「ドーパミン」の力を活用して脳をその気にさせる方法を綴った『すぐやる脳』(サンマーク出版)から一部抜粋、再構成してお届けします。
◇ ◇ ◇
何かを「決める」ことは、たとえ楽しい事柄であっても、脳にとっては〝仕事〟ですから〝負荷〟となります。その証拠に、「決めた」あとはホッとするものです。決断を終えることで、脳は心配を減らすことができるのです。
意思決定については、「大脳基底核」にある「線条体」という部位が大きな役割を果たしています。「決める」前の脳は多かれ少なかれ、不安や心配を抱えています。そのため、線条体の活動が活性化され、ネガティブな衝動に駆られたり、ネガティブな習慣に陥りがちになります。
けれども、「決める」という行為は線条体の活動を抑制するため、大脳辺縁系を鎮静させ、心を落ち着かせてくれます。
「決める」ことは、ひとつの仕事が終わること。ですから脳にとっては「うれしい」ことなのです。とはいえ、「決める」という行為は、心情的には「面倒」です。
「完璧な判断をしなければならない」「間違いがあってはならない」と思い込むことが、ストレスとなることは明らかになっています。その結果、「腹側内側の前頭前皮質が過活動になる」とされています。
一方、「ほどほどな判断でよい」「どんな判断でも大丈夫」と、ハードルを下げたときは、「腹側外側の前頭前皮質が活性化する」ことがわかっています。この状況は、脳に「状況をうまく管理できている」という肯定感を与えることになります。
結果、脳にかかっていたストレスは軽減します。まとめてみると、「決める」ことを先延ばしすればするほど、脳が不安や心配を抱え込む時間は長くなります。
早く「決める」という姿勢は、自分の脳をいたわることになるのです。ではいったい、どうすれば早く「決める」ことができるのでしょうか。
「決める」「選ぶ」をすぐできる人は、特別な能力に恵まれた人、というわけではありません。
「最適解を導き出す能力をもっているにすぎない」という事実が、科学的に証明されています。しかも、「その能力は、〝訓練〟次第で何歳からでも身につけていける」というのが定説です。「訓練」といっても、特殊なことではありません。
ここで言う訓練とは、「決める」「選ぶ」という行為を何度も繰り返すことを意味します。平たく言うと、今まで多く「決める」「選ぶ」という行為を繰り返してきた人ほど、その速度が速くなっているというだけの話なのです。