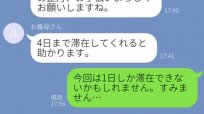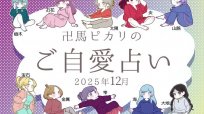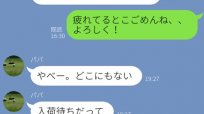職場にいるのは身分確保のため? 必要とされていない現実を直視したくない人たち
経済学者の代表的存在の1人として知られるジョン・メイナード・ケインズ(1883〜1946年)は、今から約100年前に「2030年までに平均労働時間は週におよそ15時間となる」と論文に記していた。
さまざまな分野で技術革新が進み、人が行なっている作業がどんどん自動化・効率化されていくことを見越したのかもしれない。だが、実際にはそうなってはいない。働かずにはいられない人の心理、そしてそれにつけ込む「偽仕事」がどこにでも介在していることが背景にある。
「偽仕事」を追い出して生産性と充実度が本当に高い働き方を現実世界でやり切る術を提案したデンマークのベストセラーの邦訳版『忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。
◇ ◇ ◇
デンマークの社会学者であるローランド・ポールセンによると、中身のない仕事のうち「怠け」は何もしないことである。仕事と余暇の関係について書いた20世紀はじめの社会学者、ソースティン・ヴェブレンによると、代わりに人にやらせて自分は怠けるのが上流階級の特徴だという。
上流階級はお金があり余っているので、自分たちが何もしないだけでなく、他人にもお金を払って何もせずにいさせる。主人が食事をしているあいだ、使用人は部屋の隅で石柱のように直立している。これは異常なことではなく、当時は上品なこととして肯定的に受けとめられていた。
人は今でも怠ける。たいていひそかに怠けるが、ときにはあけっぴろげに怠けることもある。
たとえば1990年代には、誇りあるIT企業はどこもオフィスにテーブルフットボールの台を置いていた。一日に1時間ほど働き、あとは互いにDJをしたりネットサーフィンをしたりする人たちのことをポールセンは語ってくれた。だが、それを隣の部署に知られるのはいやがり、こっそりとすることが多いのだという。画面の前に座り、キーボードを叩いて、色分けした予定で電子カレンダーを埋めてカムフラージュする。
完全に怠けるのではなく、別の戦略を好む人も多い──長い時間をかけてゆっくり仕事をするという戦略だ。やることがほとんどないので、仕事を引きのばすことで時間が余っているのを隠すのである。
これは時間単位で賃金を払う組織でよく見られるが、それ以外の組織にも存在する。上司の目をごまかすことだけが目的ではない。自分は実は必要とされていないという現実を直視したくないのだ。職場にいるのは何かをするためではない。職場での身分を確保するためだ。職場に通う人間でいるためである。