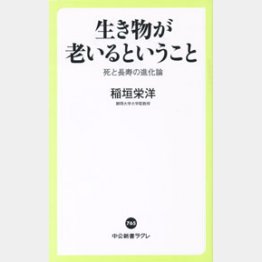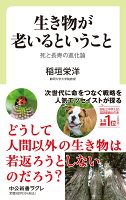老いと命の科学
「生き物が老いるということ」稲垣栄洋著
高齢化は現代社会を悩ます問題。しかし「老い」はそんなに悪いことなのか。
◇
生物の死は必ずしも老いの結果ではない。夏の風物詩のセミの鳴き声は夏が終わると聞こえなくなる。
セミは老いたわけではないのに役割を終えると死んでゆくのだ。農水省を経ていまは静岡大で教壇に立つ著者は、人間が生物界には珍しい「『老いる』ことのできる特別な動物」だという。
ペットに飼われる犬や猫も、自然界のままなら老いる前に病気や事故などで死ぬのが定め。彼らが老いるのは人間のもとにいるからなのだ。また秋にイネが黄金の穂をつけるのも、植物として老いを迎えたからこその実りなのだという。
生物としての盛りを過ぎた高齢女性も、成育期間の長い人類が「子育て」という仕事をこなす上で欠かせない「おばあちゃん」という存在として長く役割を果たしてきた。これは人類進化を説明する「おばあちゃん仮説」として認められているのだそうだ。経験と知恵のある年寄りを保護することで人類は「『寿命は長いほうが有利である』という戦略を発達させてきた」のである。
老化は悪ではなく生物としての戦略であり、老いは人間にとって「最も重要な実りのステージ」だと結ぶ。静かな元気が湧いてくる小著だ。
(中央公論新社 902円)
「ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか」更科功著
生物はなぜ死ぬのか。仮説は多数あるが、本書によると4つの説が死の根本要因を議論したという。
第1は最も常識的な「自然淘汰説」。第2は若い世代に道を譲るための「種の保存説」。第3は生きている間に使えるエネルギーを一定だとする「生命活動速度論」。第4が寿命は死亡率によって進化したとする「進化論的寿命説」だ。
カマキリのメスの中には交尾中にオスを食べてしまうものがあるが、食べられたオスのアミノ酸はメスが産んだ卵に引き継がれている。オスの死は種の保存に貢献しているわけだ。生物は自然淘汰によって環境に適応し、進化しているのである。著者は美大で教壇に立つ分子古生物学者。たとえ話が豊富で進化や遺伝のしくみを知ることができる。
(新潮社 1650円)
「いのちの科学の最前線」チーム・パスカル著
全国各地の大学で教える生物学や医学の専門家たち。その中から「10人の博士」に取材。それぞれ1章を費やして研究内容を紹介したのが本書だ。
大阪大学の生物学者は「性スペクトラム」という概念を提唱した。スペクトラムとは「境界のない連続した状態」を意味する。つまり、オスとメスの両性はくっきりと区別されるのではなく、連続したグラデーションでつながっているということだ。
東北大学の「加齢医学研究所」に勤務する医学者は「酸化ストレス応答」を研究する。心理的なストレスを与えられるとヒトの体は過剰ないし異常な酸化反応を起こす。また、呼吸で酸素を取り入れるとその一部が活性酸素に変わり、免疫や感染防御などの役に立つが、活性酸素が過剰になると体の抗酸化防御機構を上回って酸化ストレスが起こり、細胞を損傷させてしまう。がんや老化や生活習慣病はこんなメカニズムによるのだ。
著者は理系・文系まじったメンバーが集まった理系ライター集団だ。
(朝日新聞出版 935円)