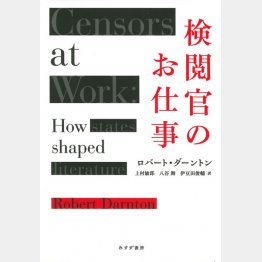「検閲官のお仕事」ロバート・ダーントン著 上村敏郎ほか訳
「検閲官のお仕事」ロバート・ダーントン著 上村敏郎ほか訳
戦前の文献を読んでいると、○○や××などの記号で伏せ字が施されたものを見かける。これは、検閲官が問題視しそうな文言や表現をあらかじめ伏せ字にして発売禁止などの処分を回避するための手段だ。それだけ戦前・戦中の日本においては国家による厳しい検閲が行われていた(戦後は占領軍による検閲が行われた)。この検閲という行為は日本に限らず、書物というメディアの登場以来、不即不離のように存在していた。
18世紀のフランスを対象とする書物の歴史・文化史を専門とする著者は、検閲の実際の担い手である検閲官に焦点を当て、検閲官がどのように仕事をし、検閲制度がどのように運用され、機能していたのかを解明していく。本書で取り上げられているのは、18世紀のフランスのブルボン王朝、19世紀のインドにおけるブリテンの統治、20世紀の東ドイツの共産主義体制という、3つの時代と地域の異なる権威主義体制だ。
ブルボン朝では、裕福で「質の高い人」に対して、王の恩寵による「特認」(=特別な施し)が与えられていたが、書籍にもこの特認が適用され、それを選出するのが検閲官の役目だ。検閲官は受け持った本に特認を与えるべく、その本の長所を引き出し、より質の高い文章とするため修正案を作者に提示するという、現在の編集者のような仕事もしていた。無論、王のお眼鏡にかなうという目的であったが、我々がイメージする検閲とは違う。同様に英領インドでは「監視」、共産主義時代の東ドイツでは「計画」という独自の文化システムの中で検閲官は自らの仕事を意味づけ、いずれも単純な言論統制ではない検閲の実態が浮上する。
検閲によって刑務所に送られたり、国を追われたりという厳然たる歴史があり、言論の自由と対立する国家権力による検閲を容認することはできないが、サイバースペース上の検閲が浮上している現在、この問題に向き合うことは必要だ。 〈狸〉
(みすず書房 5500円)