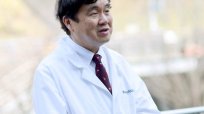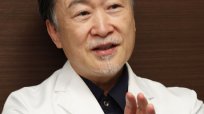(48)父の命日…1年経って、ようやくわかったこと
父親が亡くなって、まもなく1年になろうとしていた。父は夜に自分の部屋で倒れたようだった。翌朝になっても、そして1週間たっても誰にも気づかれることなく、冷たくなっていたのだ。
ずっと考えることを避けてきたけれど、あの時のことを、ようやく追体験できるかもしれない。そう思って、実家で命日を迎えることにした。父がひとりきりで過ごした1月初旬とは、どんな季節だったのだろうか。
実家は鉄筋コンクリートの建物だが、それでも一軒家の寒さは骨身にしみる。暖房の届かない廊下や脱衣所、夜のトイレに立つたび、こんな寒さのなかで父はひとりだったのだと胸が詰まった。
ひとりで過ごす一軒家の夜は暗く、恐ろしい。導入していた防犯会社のセキュリティーシステムが心強かった。しかし、きょうだいも子どももパートナーもいないと、誰かに見守られているという感覚や安心も、こうしてお金で買うしかないのも事実だった。
翌日に母の施設に届ける荷物をまとめて、懐かしい学生時代のベッドで眠っていると、夢を見た。若い息子たちが2人、あれこれと指示を出さずとも手際よく片づけをしてくれる。「ああ、私には家族がいたんだ。助かるなあ」と、心から安心していたが、目が覚めるとやっぱり誰もいない。きっと、私がもともと東京で飼っている猫たちが手伝いに来てくれたのだろうと少し笑った。