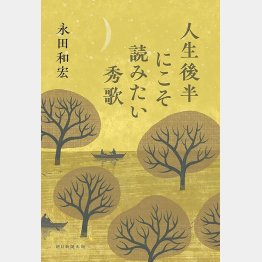志川節子(作家)
6月×日 世界遺産高野山へ、1泊2日の旅。山上盆地に広がる町並み全体が、信仰の地。インバウンドの影響で宿坊の料金が高騰、山から離れたビジネスホテルに泊まる。2日目に奥之院を参拝、生身供を見学する。即身成仏を遂げて永遠の瞑想に入ったとされる弘法大師空海へ食事を供える儀式だ。ざんざん降りだった雨が、なぜかその時だけやみ、杉木立から光が射してきた。じつに神秘的な景色。
6月×日 永田和宏著「人生後半にこそ読みたい秀歌」(朝日新聞出版 1980円)を読む。2022年、著者の青春時代を描いたNHKドラマを観た時の衝撃は大きかった。熱烈なラブストーリー。毎年1月、宮中歌会始の折にテレビで拝見する、いかめしい感じの先生というイメージが吹き飛んだ。すぐに、原作となった「あの胸が岬のように遠かった──河野裕子との青春」(新潮社 825円)を入手、以来、新刊が出るのを心待ちにしている。
歌を詠むにも、男性は老いをネガティブにとらえ、女性は軽やかに笑い飛ばす傾向があると著者はいう。もっとも、平均寿命が長くなっている近年は、男性の悲壮感も薄らいできてはいるようだが。
去年は私も、親の介護を意識したり、同世代の友人を亡くしたりして、自分の人生が後半に突入していることをひしひしと実感した。この世に生まれた以上、一定の年数が経てば老いていくのは当たり前だが、体の衰えや老後のお金、病、身近な人たちとの別れなどを考えると、憂鬱な心持ちになる。
けれど、先人たちの歌は、老いが先細っていくだけのものではないことを示してくれる。食事や酒、旅に楽しみを見出すもよし、友と心情を分かち合うもよし、秘めた恋に身を焦がすもよし。孤独の侘しさばかりでなく、孤独の充実もまた歌の題材となる。
短歌って、果実まるごとをぎゅっと凝縮したジュースみたいだ。一首に作者の人生が濃密に投影される。一首一首に異なる老いが存在し、その豊潤さに触れて、あのとき高野山で目にしたような光が射すのを感じた。