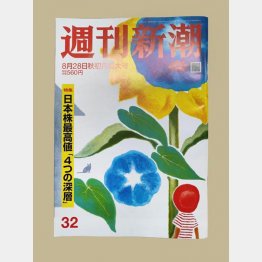高山正之コラム打ち切り…その前に週刊新潮がやるべきだったこと
編集者というのは、自分が考えていることを著名な筆者に代弁してもらうということをよくやる。編集部が高山や杉田のような人間を起用してきたのは、彼らの考えを「是」としたからである。
したがって、新潮社の「おわび」が「差別的かつ人権侵害にあたるという認識を持っていない」(深沢潮)ものになったのは“必然”なのである。
出版社系週刊誌として新潮が創刊されてから現代、文春、ポストなどが出て、1990年代は週刊誌黄金時代といわれた。しかし、現在、ABC調査によると文春の実売部数が約17万部、新潮にいたっては10万部を切っているという。新潮社の社論を代表する雑誌ではあっても、休刊の噂が絶えることはない。
新潮社に問いたい。新潮は創刊以来「タブーに挑戦」とうたって、新聞やテレビにできないことをやってきた。
記者クラブの閉鎖性を批判した。1980年、長野県で起きたOL誘拐殺人事件では、事件発生してすぐに新聞、テレビは警察当局にいわれて報道協定を結んだ。だが、この協定が3週間の長きに及び、警察の初動捜査のまずさを隠すためだったとして、新潮はこの事件をすっぱ抜いた。