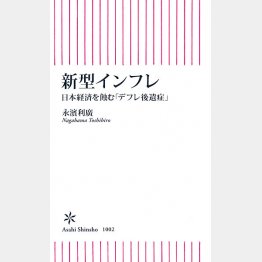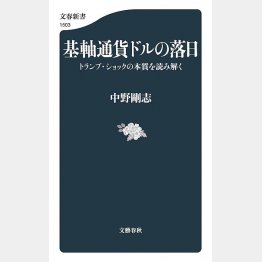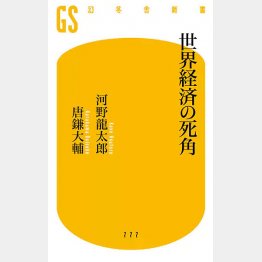不安定化する経済
突然の急激インフレに、トランプ2期目のデタラメ政策で経済はいまや不安定の極みだ。
◇ ◇ ◇
「新型インフレ」永濱利廣著
「新型インフレ」永濱利廣著
インフレは本来、需要増によるのが健全。これがディマンドプルだ。しかし今の日本のインフレは需要が拡大してないのに物価だけが上がっている。背景はウクライナ戦争による世界的なインフレや、円安による輸入品の価格上昇がある。つまりコストばかりがかかることによるコストプッシュ型のインフレが今なのだ。
実際、2年前に春闘で30年ぶりの賃上げ率をかちとったり、初任給アップに踏み切る企業が増えたりしているのに、人々の間には賃金が上がったという安心感がなく、そこにデフレでしみついた節約志向が拍車をかけているのだと著者はいう。現に景気のいい話は大企業に偏っているが、労働者の7割は中小企業で雇用され、突如のインフレの中で身を硬くしているのだ。豊かであっていいはずの社会で、大半の人が豊かさを実感できないでいる。これが現在の状態で、これを著者は「新型インフレ」と呼ぶわけだ。著者は生保系シンクタンクの研究員。 (朝日新聞出版 1045円)
「基軸通貨 ドルの落日」中野剛志著
「基軸通貨 ドルの落日」中野剛志著
2期目の米国大統領に就任以来、世界を脅し続けるトランプの高関税政策。通常の外交は複雑な状況の中、短・中・長期的な利益を考えて行うものだが、トランプは短期的利益のための取引で経済を翻弄する。
それができるのはドルが基軸通貨だからだ。第2次世界大戦後の80年間、ドルはニクソン・ショックなどの大変化を経由しつつも基軸通貨であり続けてきた。多くの識者はトランプの経済政策は失敗するとみる。本書の著者も同意する。
しかしトランプの失敗後に、リベラルな国際経済秩序が戻るという期待とは裏腹に、経済評論家としてグローバリズムに警鐘を鳴らす著者は旧秩序の崩壊が決定的になるとみる。
著者によればトランプ政策の裏付けは「マールアラーゴ合意」。トランプ自慢の別荘地の名を冠したこれはドル安誘導を提唱し、関税引き上げによる自国通貨高が輸入インフレを相殺するのに加え、関税で収入が増えるともくろむ。普通、高関税は自国の産業保護を目的とするが、トランプは日銭稼ぎが目当てなのだ。
著者はこの政策を裏付けるトランプ政権内の経済理論を詳細に検討し、その欠陥を暴く。そのスリリングな展開の後に待ち受ける恐怖は底なしだ。 (文藝春秋 990円)
「世界経済の死角」河野龍太郎、唐鎌大輔著
「世界経済の死角」河野龍太郎、唐鎌大輔著
外資系証券とメガバンクのシンクタンク・アナリストが対談形式で語るのはドル基軸体制の終焉と日本経済の不透明な見通し。日本企業はとかく「生産性が低い」と批判されるが、実はこれは誤解という。
日本よりも生産性の低い欧州各国では実質賃金は日本ほど低くない。生産性が低いから日本にはグーグルやアップルが生まれないという批判も、欧州にだって生まれてないと反論する。
問題は生産性ではなく、日本企業がいまなお長期雇用制を維持し、それを優先して実質賃金の伸びを抑えているからだ。
1990年代末の金融危機によって高度成長期を支えたメインバンク制は破綻したはず。にもかかわらず日本企業は長期雇用制を維持する道を選んだというのだ。とはいえ、最近はやりのジョブ型労働制に切り替えれば賃金が上がるかといえば、そう簡単な話でもない。
日本の長期雇用制は社会の安定には大きく貢献している。そういうバランスの上で賃金上昇を維持しつつインフレを抑制することこそ、エコノミストたちには知恵を絞ってほしいところだ。 (幻冬舎 1320円)