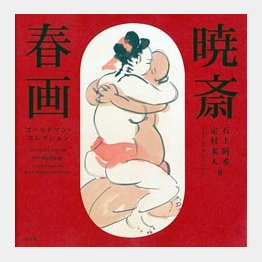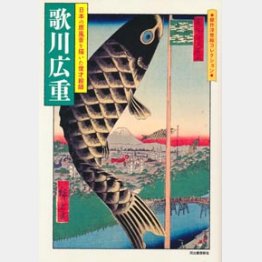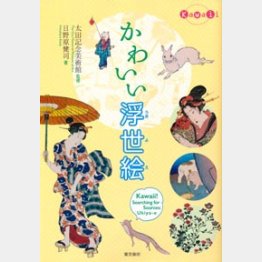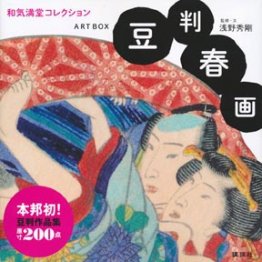浮世絵はポップカルチャーなのだ特集
「暁斎春画」石上阿希、定村来人著
浮世絵は日本が誇る芸術の極み。大胆な構図や鮮やかな色使いは、世界の名だたる画家たちをも魅了してきた。しかし浮世絵のすごいところは、これらが上流階級のためのものではなく庶民の娯楽、ポップカルチャーであったことだ。今回は江戸の庶民たちが楽しんだ春画をはじめ、素晴らしき浮世絵の世界を堪能できる4冊を紹介しよう。
性の交わりを描いた浮世絵を「春画」と呼ぶようになったのは、明治に入ってからのこと。春画を卑猥なものとして取り締まりが強化された明治後期には、「秘戯画」などの呼称も生まれた。
しかし、これより以前の時代には、「春画」に「わらいゑ」とふりがなをふるのが一般的だったという。性を喜び、面白おかしく受け入れる。そんなおおらかな時代の春画を受け継いだ最後の浮世絵師といえるのが、幕末から明治にかけて活躍した河鍋暁斎だ。
石上阿希、定村来人著「暁斎春画」(青幻舎 2500円+税)では、暁斎の作品を集めた個人コレクションとしては世界最大かつもっとも充実した内容を誇る、イスラエル・ゴールドマン・コレクション所蔵の春画すべてを掲載している。
暁斎の春画における笑いの種類は実に多彩だが、ばかばかしさが突出した作品群といえば「大和らい」だ。各作品とも表裏両面が楽しめる作りで、表面の絵の一部が動かせる仕掛け絵になっている。
たとえば、後背位でまぐわう男女の絵。気持ちよさそうな表情の男の顔の部分の仕掛けを引っ張ると、女の尻から黄色い屁が放出され、男はのけ反り苦悶の表情を浮かべる。裏面には、屏風の陰で勃起しながらのぞきをしていた男が、鼻をつまんで逃げようとしている絵が描かれている。時を超えた現代の私たちも、十分に笑わせてくれる作品だ。
暁斎は明治3年、泥酔して描いた作品が身分の高い人を笑いものにする絵であったとして、投獄の憂き目に遭っている。しかし、滑稽やおどけの陰に鋭い風刺を込めるのは、暁斎作品には付き物。元治元年に描いた「稚児男色絵巻」では、僧たちが蹴鞠で遊ぶ稚児たちをほほ笑ましく眺める風景から一転して、ハチャメチャな乱交が繰り広げられていく。
僧ひとりで4人もの稚児を相手にするさまや、僧たちが男性器の大きさを競う「陽物比べ」に興じる場面などが躍動感たっぷりに描かれていくが、この作品でとくに注目したいのが締めくくりの絵。もったいぶった顔をした高僧が、仏まで犯しているのだ。組織としての寺に向けられた風刺であるというが、なかなか強烈な作品だ。
幕末から明治という日本の大変動期に、ウイットとユーモアを縦横無尽に描いた暁斎の春画。その魅力を、ぜひ堪能して欲しい。
「日本の原風景を描いた俊才絵師歌川広重」河出書房新社編集部著
歌川広重といえば、江戸から京都までを旅して描いた「東海道五十三次」があまりにも有名だが、この作品をより深く見てみると風景の描写だけでなく、日本の繊細な気候が見事に描き分けられていることにも気づく。「大礒」の副題である「虎ケ雨」は、遊女が恋人の命日に流す涙という意味を持つが、その恋人の命日は梅雨時の5月28日。描かれる雨は、どんよりした空からまばらに落ちている。一方、傑作と名高い「庄野」の副題は夏の季語で夕立を意味する「白雨」。豪雨で遠くの景色もけむり、激しく地面を叩く雨音が聞こえてきそうな迫力だ。
雪や月、霧に風などの優れた描写も多い広重作品。日本の原風景を楽しみたい。(河出書房新社 2500円+税)
「かわいい浮世絵」日野原健司著 太田記念美術館監修
世界に通用する言葉となった「かわいい」をキーワードに、現代人にも楽しめる浮世絵ばかりをご紹介。
あなたが生き物好きであるならば、浮世絵との距離はぐっと近くなる。
何しろ浮世絵には動物や魚が題材の作品が数多い。歌川国芳作の「金魚づくし さらいとんび」では、子供の金魚をおんぶするお母さん金魚や、杖をつくおじいさん金魚など、登場するのが金魚ばかり。タイトル通り油揚げをさらい飛び去るのも、金魚。胸びれで羽ばたく姿が可愛らしいことこの上ない。力士も行事もウサギで描く歌川芳藤「兎の相撲」、体は人間の鳥たちがかくし芸を披露する歌川芳幾「諸鳥 芸づくし」など、ユル~くかわいい浮世絵が満載だ。(東京美術 1800円+税)
「豆判春画」浅野秀剛監修・文
美術展では額に飾られた大きな浮世絵を目にするが、こと春画に関しては、庶民が気軽に楽しめる手のひらサイズの「豆判春画」も数多く生み出されてきた。
その大きさは、9~9.5センチ×12.5~13センチほど。今でいえばスマホでエロを楽しむといったところか。
豆判春画は論文研究などがなく、どれだけの作品が生み出されてきたのか明らかになっておらず、作者不詳なものがほとんど。とはいえその質は確かなもので、江戸の春画のエッセンスが凝縮されている。あり得ない体位で、あり得ない場所で行為に及ぶといったおおらかな作品も多い。
本書では、豆判春画ばかりを原寸大で200点紹介。春画の新たな楽しみ方に目覚めそうだ。(講談社 2300円+税)