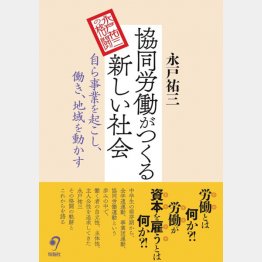「協同労働がつくる新しい社会」永戸祐三著/旬報社(選者:佐高信)
今こそ顧みられるべき「共生の思想」
「協同労働がつくる新しい社会」永戸祐三著
もう一度会いたかった。6月13日に初めて著者と会ったその対話はユーチューブで流れる「佐高信の隠し味」で見られるが、2歳下の永戸は7月に急逝してしまった。
中央大学の夜間部時代は学生運動に熱中し、全日本自由労働組合(全日自労)の本部に書記で入り、失業対策事業として始まった「ニコヨン」の労働組合運動を進める。この組合の機関紙は「じかたび(地下足袋)」だった。
「全日自労は共産党とされていたが、現場には創価学会員がいちばん多いように感じた。社会党系の人も自民党系の人もかなりいた。被差別部落の人、朝鮮人などのほか、ヤクザも多く、山口組など現役幹部が委員長をつとめている県本部も2つあった。ありとあらゆる底辺層の人、その周囲のありとあらゆる人間がいる。言葉はおかしいが、“人種のるつぼ”と感じた」
永戸がそう回顧する人たちの間で、彼は「なぜかすぐ溶け込み、どこでも人気者になった」という。その語り口に接すれば、さもありなんと思うだろう。
失業対策事業が打ち切られた後、全日自労は自治体からの清掃事業を請け負って、いわば働く者が主人公の運動を進める。その過程で永戸は「経営は怖い」ことも実感した。
トイレ掃除のやり方を永戸に教えてくれた女性は、この仕事に誇りをもっていて、こう言った。
「男性の小便器の場合は菊座の後ろに尿石がくっつく。洋式だと、座る台ののり面につく。そのことを知っていても、隠れているところだから、サボってやらない。それを私たちはちゃんとやってる」
内橋克人の「共生の大地」(岩波新書)に永戸たちの「労働者協同組合」が取り上げられている。
「労働者自身が出資し、管理し、運営し、社会に役立つ事業をおこなうという労働をテーマにした協同組合」であり、そこで働く労働者は「もはや雇用労働者でもなく、賃金労働者でもない」。
資本が労働を雇うのでなく、労働者協同組合はこれを逆転させて、労働が資本を雇うのである。
弱肉強食の原始的な新自由主義がはびこり、何とかファーストというジャングルのような自由が横行しているいまこそ、永戸の実践したこの共生の思想が顧みられるべきだろう。 ★★★