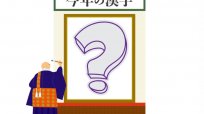数字の裏にカラクリあり 有効求人倍率「1.52倍」の実態

「43年ぶりの高水準」――。こんな威勢のいい言葉が躍っている。
厚労省が7月の有効求人倍率が1.52倍だったと発表した。1974年2月以来、43年5カ月ぶりの高水準だ。有効求人倍率は仕事を求めている人ひとりに対し、企業から何人の求人があるかを示す数字。倍率が高いほど仕事が…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り942文字/全文1,083文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。