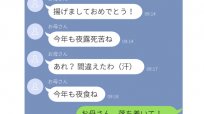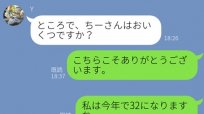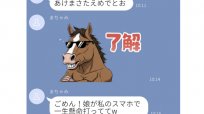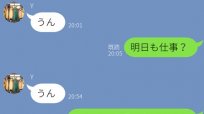部下との関係が不安…在宅勤務で試される上司の“信頼残高”
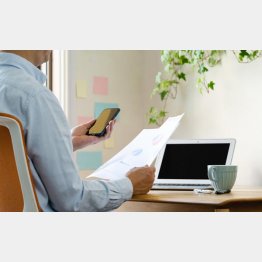
大手企業では、テレワークが働き方の柱になりそうだ。日立は7月まで国内従業員3万3000人のうち7割をテレワークとする方針を発表。来年4月以降も5割を維持するという。そんな中、IT大手の一角GMOインターネットグループは、1月末から続けていた全社テレワークを縮小。出社する人数を3…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,324文字/全文2,465文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。