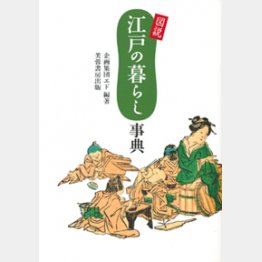「図説 江戸の暮らし事典」企画集団エド編著
懐かしいダイヤル式の黒電話も、初めて見るスマホ世代の若者には、どうやって使うのかも分からない謎の物体に見えるらしい。道具とはその時代時代の人々の暮らしぶりを、もっとも分かりやすく伝える最高のタイムマシンなのかもしれない。
本書は、江戸時代に使われた道具を紹介する事典。1000点もの写真・図版などで、当時の人々の暮らしに触れる。
各家庭に水道、ガス、電気のライフラインなどは、もちろん通じてはいない江戸時代。
夜、「とぼし油」と呼ばれる植物油を燃やして明かりをとるのが「行燈」。
枕元に置いて常夜灯として使用する「有明行燈」や、小堀遠州考案とされる茶席用の「遠州行燈」、優雅な曲線が特徴の女性用、そして携帯用枕行燈など。行燈ひとつとっても、実用品から凝った意匠の逸品まで多種多様な品々が並ぶ。
近頃は、オール電化で家の中から炎も消えてしまったが、昔は火はとても貴重だった。ライターどころかマッチもない時代、石英石類と鋼鉄をぶつけて出した火花を燃えやすいものに移して火をおこした。この「火打」の道具と付け木を一緒に収納した箱は家庭には欠かせない所帯道具だった。
こうした日用品から、武士が衣服や寝具を持参して登城する折に下僕に持たせた「挟箱」、根付で腰につける携帯可能な「印籠時計」、そしていつの時代も左党はいるもので、携帯用の酒入れ「酒筒」(中には現代のスキットル型をしたものまである)など。自作したと思われる素朴な出来栄えのものもあるが、多くは職人技が光る品々で、そのひとつひとつに「用の美」を感じる。
道具を介して、江戸の人々の暮らしと現代をつなぐ、子供と一緒に読みたい事典。
(芙蓉書房出版 2500円+税)