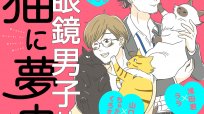森林浴と森林療法そして森林セラピー その目的や違いは?
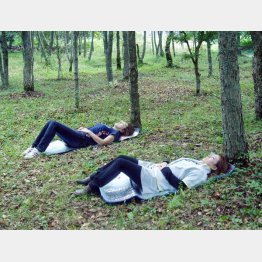
長野県木曽郡上松町の赤沢自然休養林には「森林浴発祥の地」という石碑が立つ。一方で「森林セラピー基地」という看板もあった。この2つはどう違うのだろう。
今回は、ちょっとしたウンチクを披露しよう。
森林浴という言葉をつくったのは当時の林野庁長官・秋山智英氏。森を歩く…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り894文字/全文1,035文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。