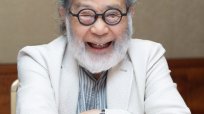近代洋画の父・黒田清輝は法律家をめざしていた
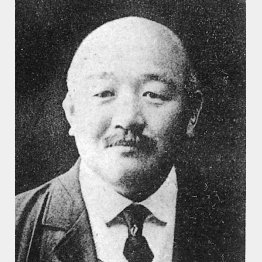
日本近代洋画の父といえば、黒田清輝(1866~1924年)だが、初めは絵描きをめざしていなかった。父は、薩摩藩奉行役から明治政府の官僚になった人物で、黒田は英語と法律を学んでいた。明治17年にフランスに渡ったのは、法律の勉学のためだった。ところが、先にパリにいた画家たちに「君が…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り453文字/全文594文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。