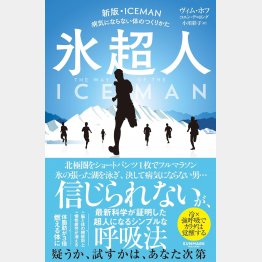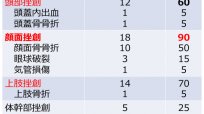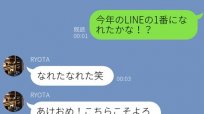驚異の体をつくる「コールド・トレーニング」…エネルギーや頭髪の充実、メンタルになぜ効果的?
体内に張り巡らされた血管という「交通網」を活用せよ
人体には、およそ12万5000キロメートル分の血管が走っている。端から端までつなげたら、なんと地球を3周できるほどの長さだ。これらの血管すべてによって、体内にある無数の細胞に充分な栄養素と酸素が届けられ続けている。もし全身の血行が良好なら、栄養素と酸素が必要な部位に必要なだけ届くため、身体は問題なく機能する。脳はよく働き、筋肉や腸、心臓、肝臓なども同じように十全に働くだろう。
動脈と静脈の膨大なネットワークこそ、身体の多くの機能を正常に働かせるうえで必須のものだ。血管の通りがよく問題なく血液がめぐっていれば、全身によい効果がある。最もよく知られている動脈は、直径2センチを超え、心臓とほかの動脈をつないでいる大動脈だ。冠動脈は、心臓の筋肉に血液を提供する役割を果たす。脳は大脳動脈を通して血液を受け取っている。このように血管は、幾度も枝分かれして全身に血液を届けている。
身体の末端にある細かい血管は毛細血管と呼ばれ、その直径は髪の毛の10分の1ほどしかない。栄養素と酸素は、この毛細血管の薄い壁を通過して細胞に運ばれる。酸素を届けた血液は二酸化炭素と老廃物を受け取り、静脈を通って心臓に戻る。そして門静脈によって腸から肝臓に運ばれ、有害物質ができるかぎり取り除かれる。
これらは低温と、どんな関連があるのだろうか。
たとえば冷たい湖に入るなどして低温にさらされると、身体はガタガタと震え呼吸は荒くなる。さらに、自動的に生命維持にかかわりの薄い部分への血流を止める。体幹の深部温度を35度以下に落とすことは死に直結するのだから、そうせざるを得ない。小指の先にまで充分な血液を届けるよりも、心臓を動かし続けることのほうが、ずっと大切だからだ。あなたの身体には、心臓など生命維持に必須となる臓器の活動を優先するだけの賢さがある。
こうして四肢につながる動脈が収縮し腕や足に供給される血液が減ることで、生命維持に欠かせない臓器──すなわち心臓や肝臓、肺、腎臓など──は機能し続けられるだけの温かな血液を確保できる。四肢への血流が制限されると腕や足がうずき始め、やけどしたかのような感覚があるかもしれない。だが再び身体が温まれば血管は拡張し、血行は通常の状態に戻る。
◼️身体を低温にさらすと活力がみなぎる
身体を低温にさらす習慣がつくと、血管は強制的に何度も閉じたり開いたりすることになる。これは筋肉を鍛える筋力トレーニングのようなものだ。慣れるまでは痛みをともなうし、トレーニング直後は疲労でむしろ弱くなったかのように感じるが、回復したら実践前よりも強くしなやかになる。
筋力トレーニングを習慣化すると、筋力が増した恩恵をつねに得続けられるのと同じように、血管は低温にさらされていないときでも拡張し続けやすくなる。つまり全身の細胞に充分な栄養素と酸素が届けられ続けるわけだ。
定期的に「コールド・トレーニング」をしている人は、ほぼ例外なく前より寒さを感じなくなったと話す。さらに、低温に鍛えられエネルギーが「増加」した話や低温が気分に好影響を及ぼしたという話を、実践者たちから幾度となく聞いてきた。
ただ、どれほど効用があるとしても低温は危険でもある。「コールド・トレーニング」は段階を追って取り組めば得るものが多いが、一足飛びに結果を求めるのは危険だ。トレーニングもせずに極度の低温に長くさらされすぎると、低温によるダメージを受けるリスクが高まってしまう。体幹深部の温度が35度以下になると、低温が骨まで達して体内の組織が死ぬ場合もあるからだ。
たとえばヒマラヤなどの高い山脈への登山では、あまりの低温に手や足の指が凍傷になることがある。最初は指が白くなり、やけどやうずきのような感覚に襲われ、しばらくすると完全に何も感じなくなる。こうなると危険だ。手当てを受けないと皮膚が黒ずみ、真っ黒になることさえある。まるでやけどしたかのように。
もちろん、低体温症(体幹深部の温度が35度以下になること)の影響は指に表れるだけではない。心拍数は下がり呼吸が緩慢になる。最終的には意識を失い、1時間後には死に至る。何の訓練もしていない人が氷温の水に入ると、この過程はもっと速い。
ヴィム・ホフは1時間半も氷の詰まった水槽のなかに座っていながら、体温を常時37度に保てる。心拍数や血行もソファでくつろいでいるときと変わらない。
▽ヴィム・ホフ(Wim Hof) 1959年、オランダ生まれ。極寒に耐えられる能力を活かし、現在20もの世界記録(北極圏でのハーフマラソンのタイムや、氷の詰まった浴槽に居続けられる時間など)を保持しており、その様子がBBCにも取り上げられTEDで語られた。こうした偉業のほか、人体への効果が科学的に証明されたヴィム・ホフ・メソッドの考案者として世界中の何万もの人々に感銘を与え、「呼吸エクササイズ」と「コールド・トレーニング」の実践を通して、彼らが失いかけていた生命力を取り戻させてきた。共著書に『アイスマンになる(Becoming the Iceman)』がある。
▽コエン・デ=ヨング(Koen De Jong) アムステルダム在住。呼吸とランニングに関する6冊の著書があり『マラソン革命(Marathon Revolution)』はオランダでベストセラーになった。ヴィパッサナー瞑想の実践者でもある。ヴィム・ホフに出会って以来、寒中水泳を楽しむようになった。愛読書はミヒャエル・エンデ『モモ』。
▽小川彩子(おがわ・あやこ) 学習院大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士後期課程単位取得退学。翻訳者。おもな訳書に『ハーバード集中力革命』(サンマーク出版)、『メジャーリーグの書かれざるルール』(共訳、朝日新聞出版)、『一流のプロは「感情脳」で決断する』(共訳、アスペクト)、『世界の名画 1000の偉業』(共訳、二玄社)、『結婚したい。でも、愛だけじゃ結婚できない』(オープンナレッジ)、『電子メールプロトコル詳説』(ピアソン・エデュケーション)などがある。そのほか技術文書の翻訳や翻訳書の編集などに携わっている。